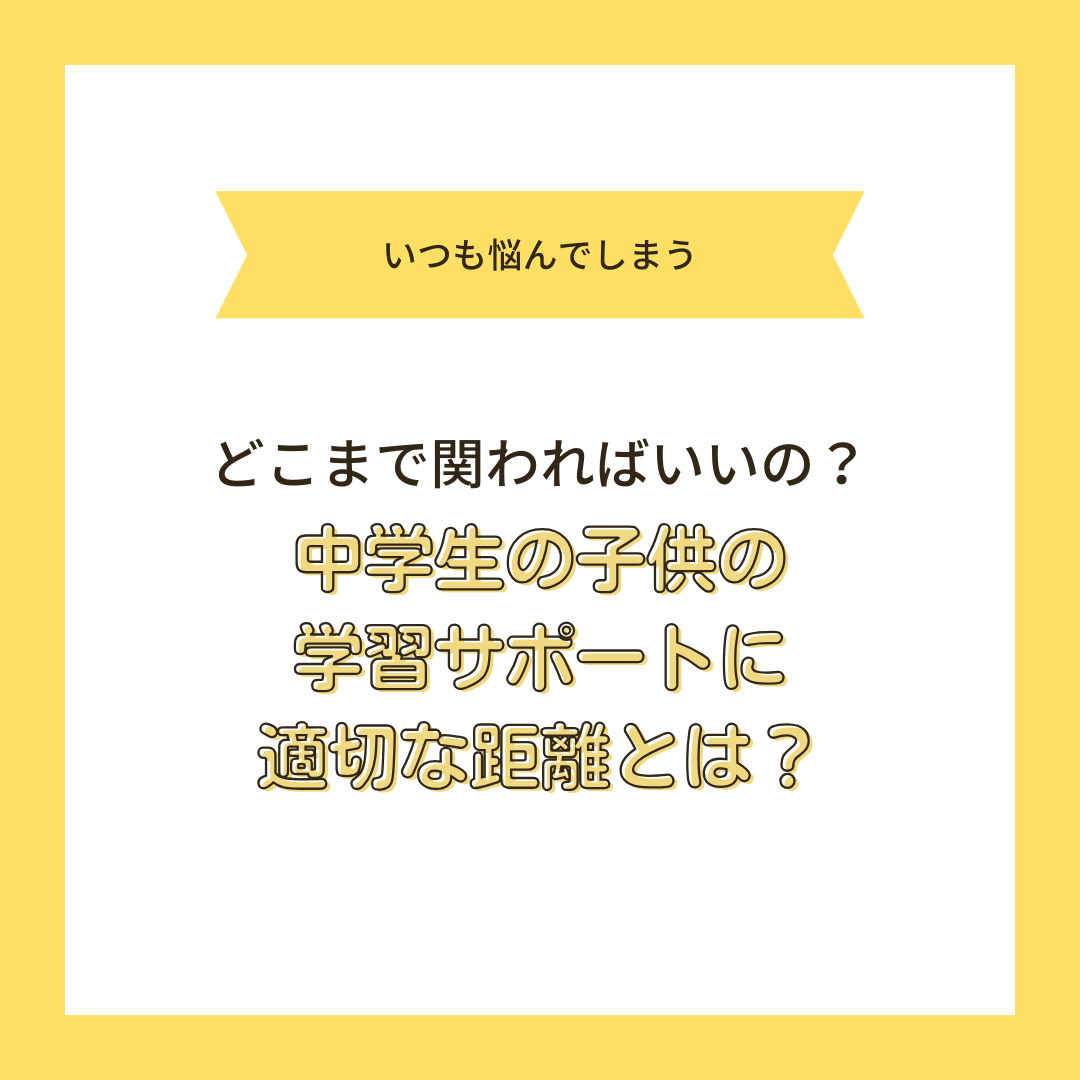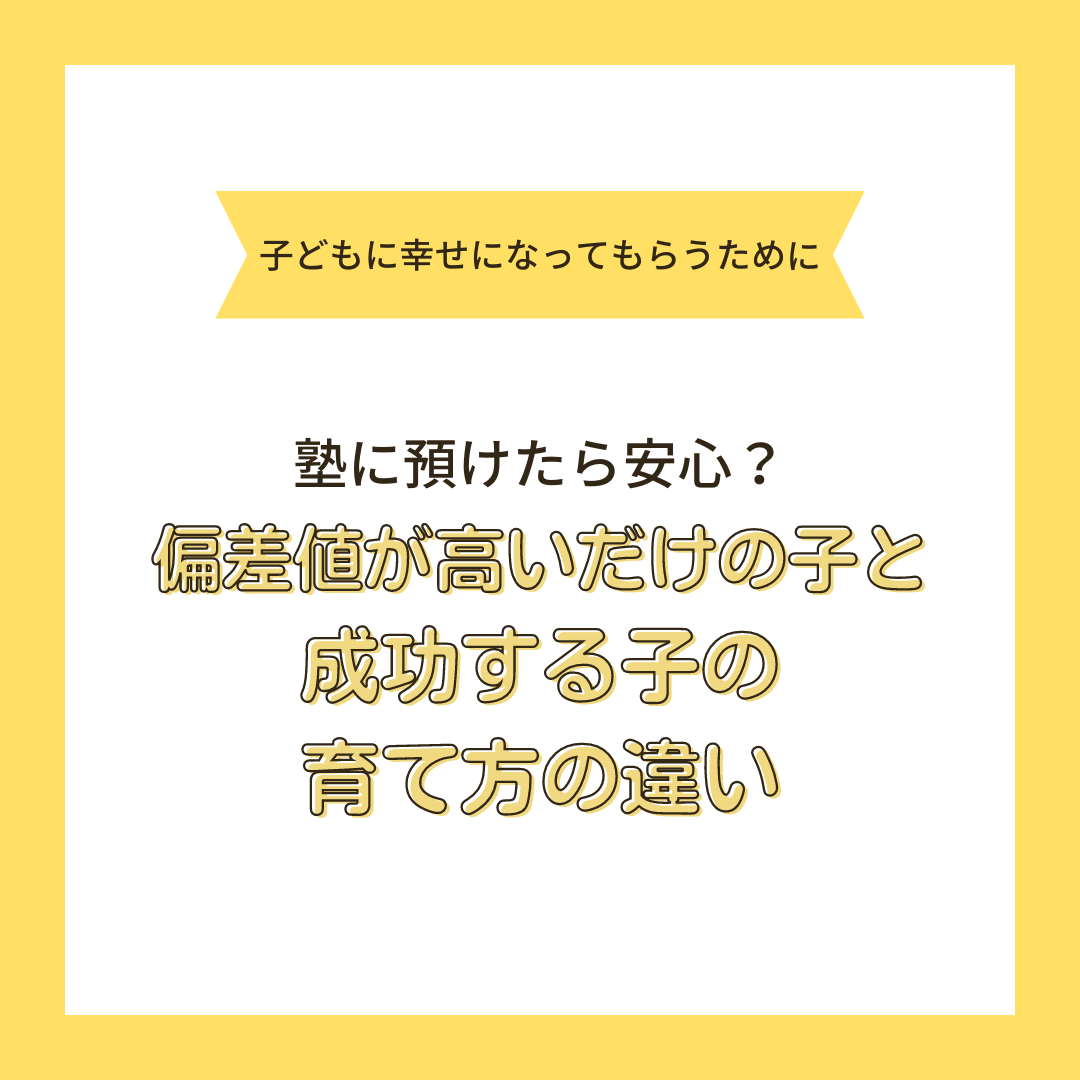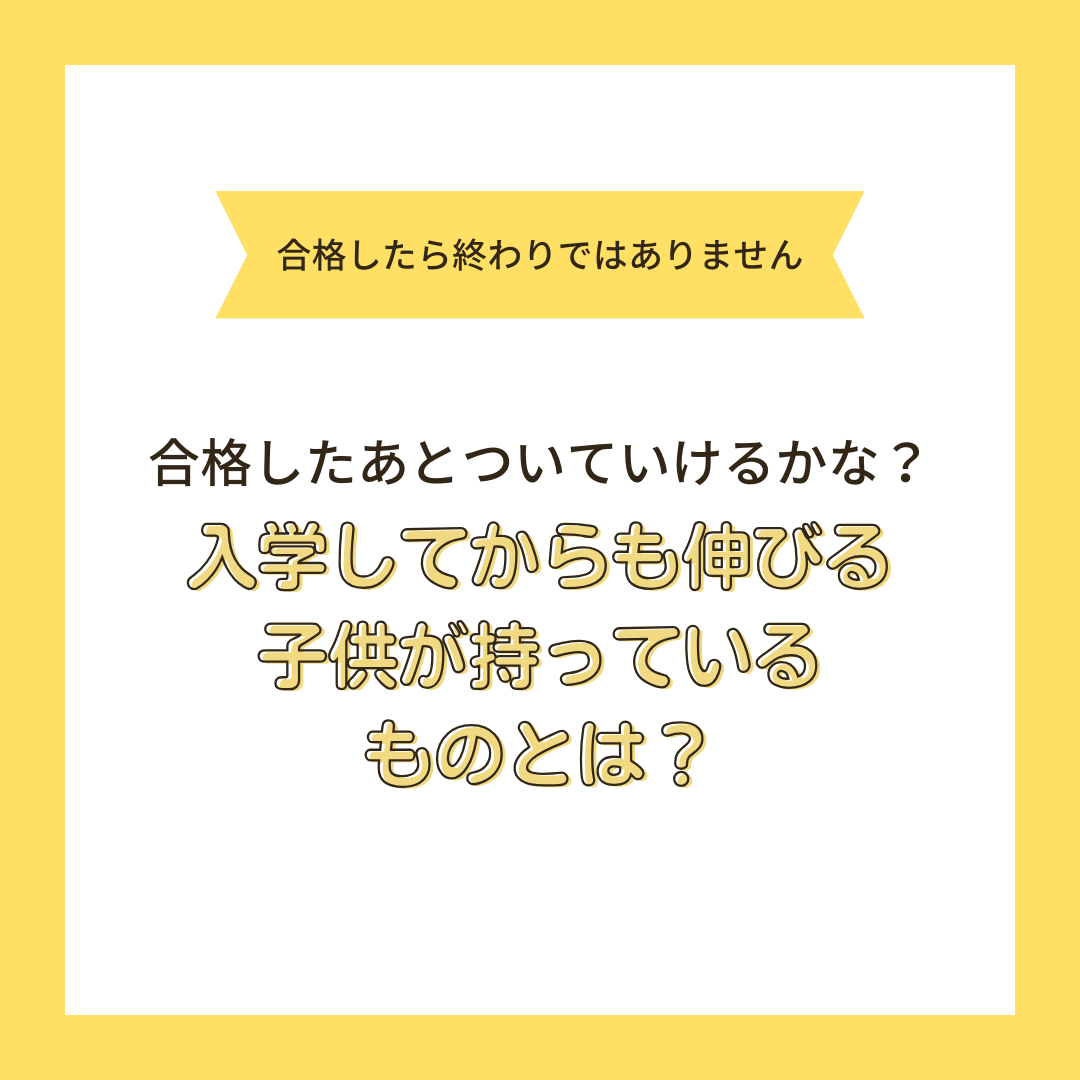こんにちは
自己肯定感を高めるオンライン学習塾Cheers!の塾長のかつ師匠(@cheers.school)です
お子さんが中学生になると、学習面でのサポートが一段と重要になりますよね。
でも、どれくらいの距離感でサポートするのがベストなんでしょうか?
「目を離さず、手は出さず」というスタンスは、中学生の学習サポートにおいて重要なポイントです。
このフレーズを聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどういう意味で、なぜこれが重要なのか、詳しく掘り下げていきましょう。
1. 「目を離さず、手は出さず」とは?
「目を離さず、手は出さず」という表現は、子供の成長と自立を促す上での理想的なサポートの距離感を指します。これは、親が常に子供を見守りながらも、必要以上に手を出さないことを意味します。簡単に言うと、子供が自分で問題を解決できるようにサポートするが、実際の手助けを最小限にするということです。
例えば、ショッピングモールの優れたショップ店員を思い浮かべてください。お客さんが何かを探しているのを見て、近くで商品を整理しながら、お客さんが困った瞬間にサッと助けに入る、そんな振る舞いです。このように、親も子供の学習を見守りつつ、必要な時にだけ手を差し伸べるのが理想的です。
2. 具体的な実践方法
中学生の学習をサポートする際に、この「目を離さず、手は出さず」のスタンスをどう取り入れるか、具体的な方法をいくつか見てみましょう。
a. 日常の学習の見守り
子供が自分の部屋で勉強している時、親は近くのリビングで家事をしたり、本を読んだりするのが一つの方法です。これにより、子供は親の存在を感じつつも、自分で課題に取り組むことができます。親は子供が質問をしたり、助けを求めたりした時にだけ対応するようにします。
b. 目に見えないサポート
学習環境を整えることも重要です。静かな勉強スペースを提供したり、必要な教材を揃えたりすることで、子供が集中して勉強できる環境を整えることが、間接的なサポートとなります。これも「目を離さず、手は出さず」の一環です。
c. 反応を見逃さない
子供がどのように学習に取り組んでいるかを観察し、困っている兆候がないかを確認することも大切です。例えば、宿題に取り組む時間がいつもより長かったり、イライラしている様子が見られたら、声をかけて状況を確認するのも良いでしょう。ただし、ここでも直接手を出すのではなく、アドバイスをする程度にとどめます。
3. 失敗を恐れずに見守る
子供は自分の力で問題を解決することで、学び、成長します。親が手を出しすぎると、子供は自分で考える力を養う機会を失ってしまいます。多少の失敗は成長の一部として受け入れ、子供が自分で乗り越える経験を積むことが大切です。
統計的にも、親の過干渉が子供の自立を妨げることが示されています。例えば、ある研究では、親が過度に手を出すことで、子供の問題解決能力や自信が低下することが報告されています。これを防ぐためにも、子供が自分で解決策を見つけるのを見守ることが重要です。
4. 協力の重要性と注意点
「目を離さず、手は出さず」のスタンスを維持しつつも、時には親子で協力して取り組むことも必要です。しかし、親子が協力する際には、以下の2点に注意しましょう。
a. 最終目標を共有する
親と子供が協力して学習に取り組む場合、最終的な目標は子供の自立です。これをお互いに理解し、共通の認識として持つことが大切です。例えば、ある期間だけ親がサポートし、その後は自分でできるようになることを目指す、といった具体的なプランを立てると良いでしょう。
b. 共依存を避ける
親があまりにも関与しすぎると、子供が親に依存してしまうことがあります。これを避けるためには、子供が自分の力で問題を解決する機会を増やし、親が必要な時にだけサポートする姿勢を保つことが重要です。
結論
中学生の子供の学習サポートにおいて、「目を離さず、手は出さず」という距離感は、子供の自立と成長を促すための鍵です。親が子供を見守りつつ、必要な時にだけサポートすることで、子供は自分で考える力を養い、将来的に自立した大人になる準備をすることができます。このバランスを保つことは簡単ではありませんが、少しずつ実践してみることで、親子ともに成長できる素晴らしい機会になるはずです。皆さんもぜひ、試してみてくださいね!