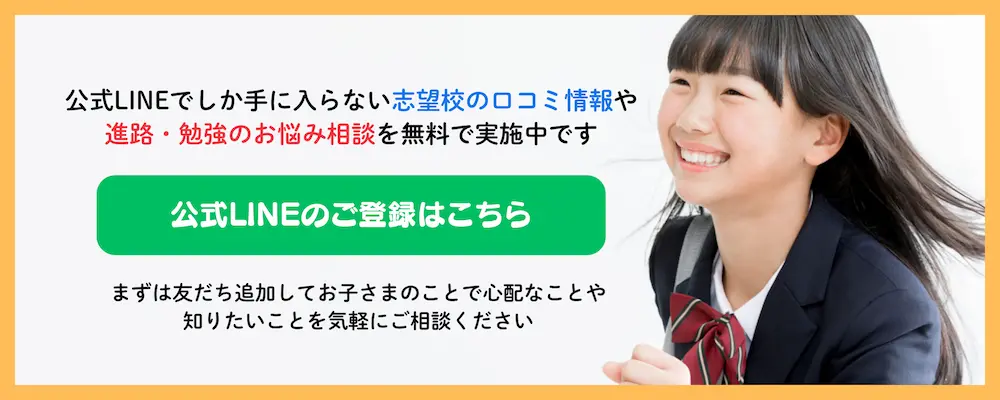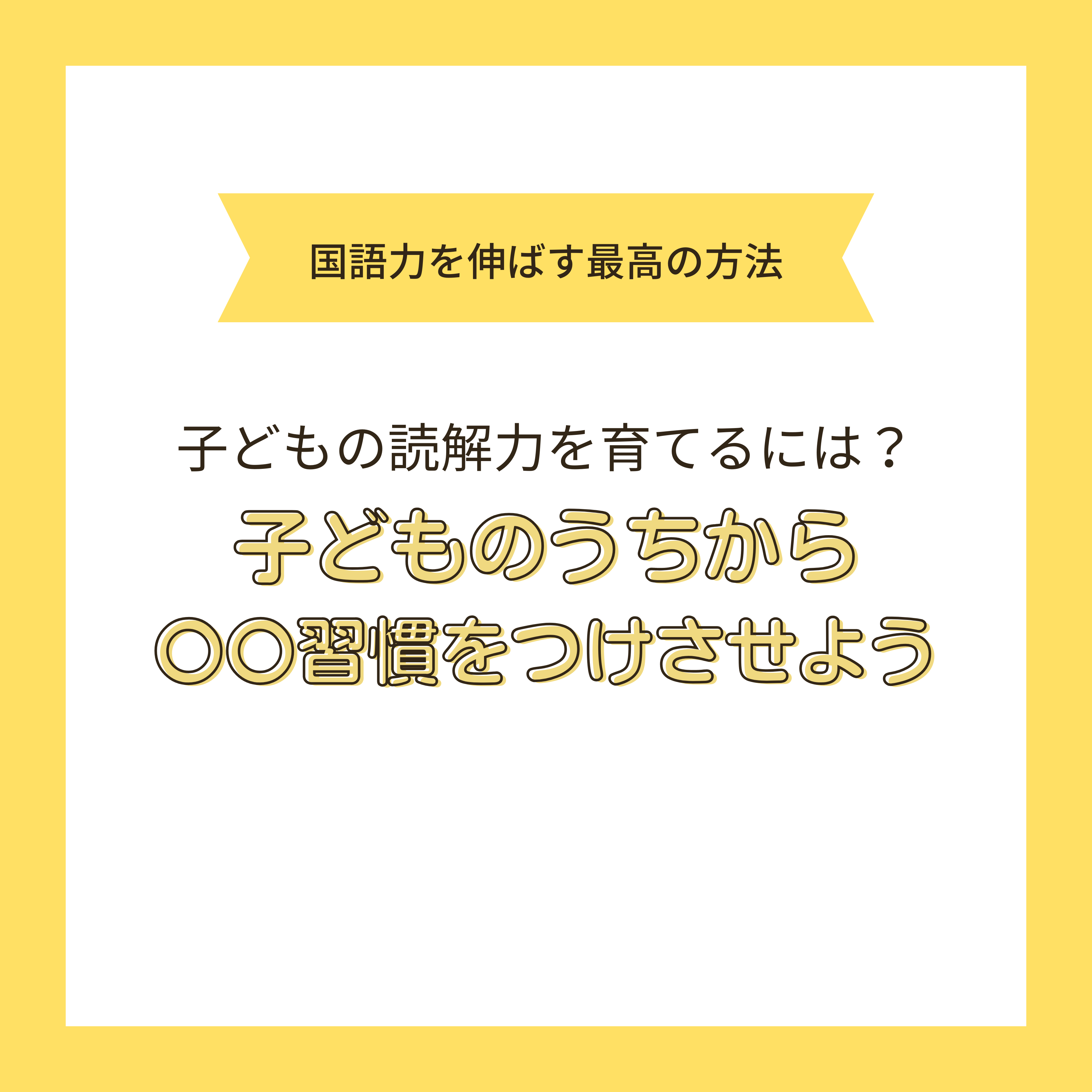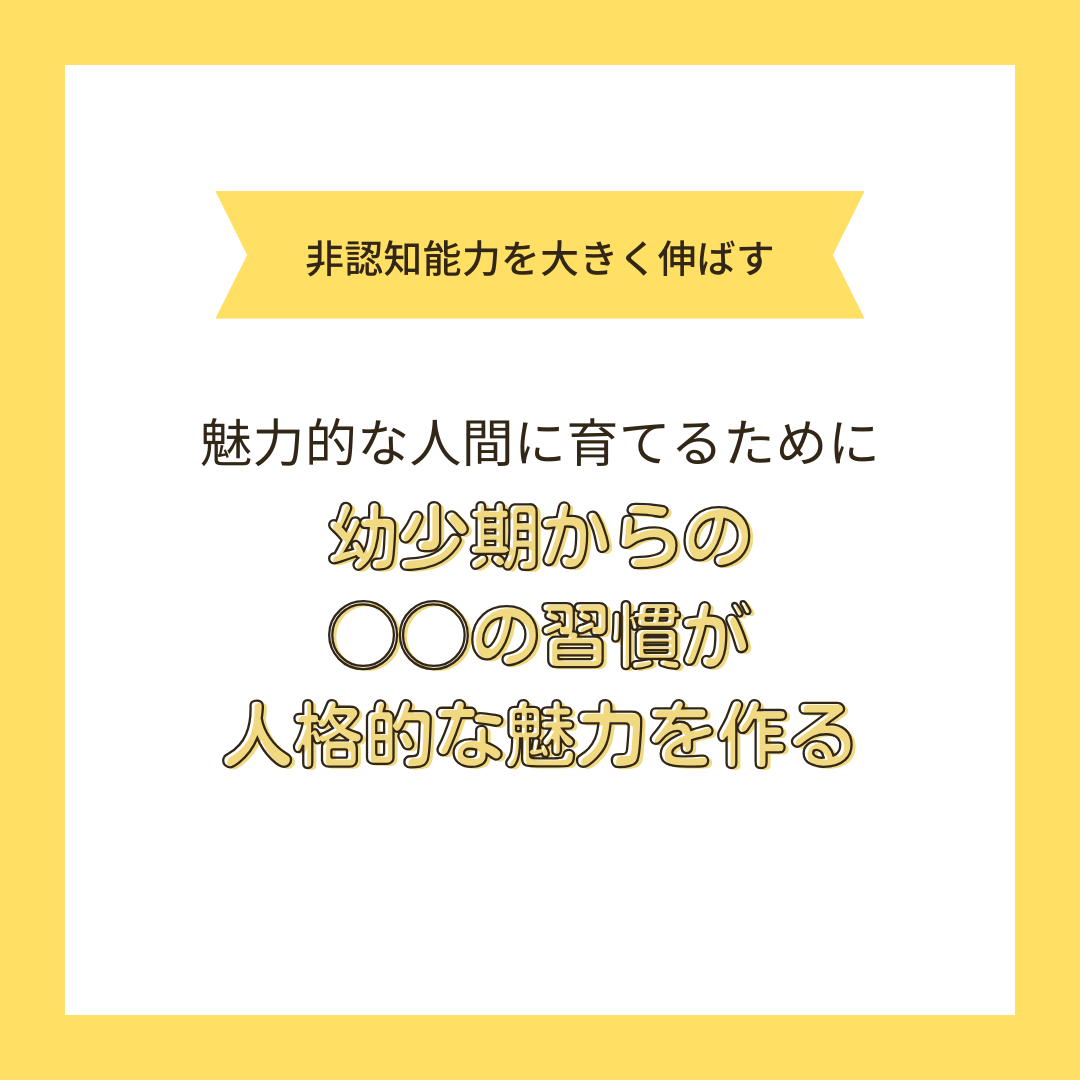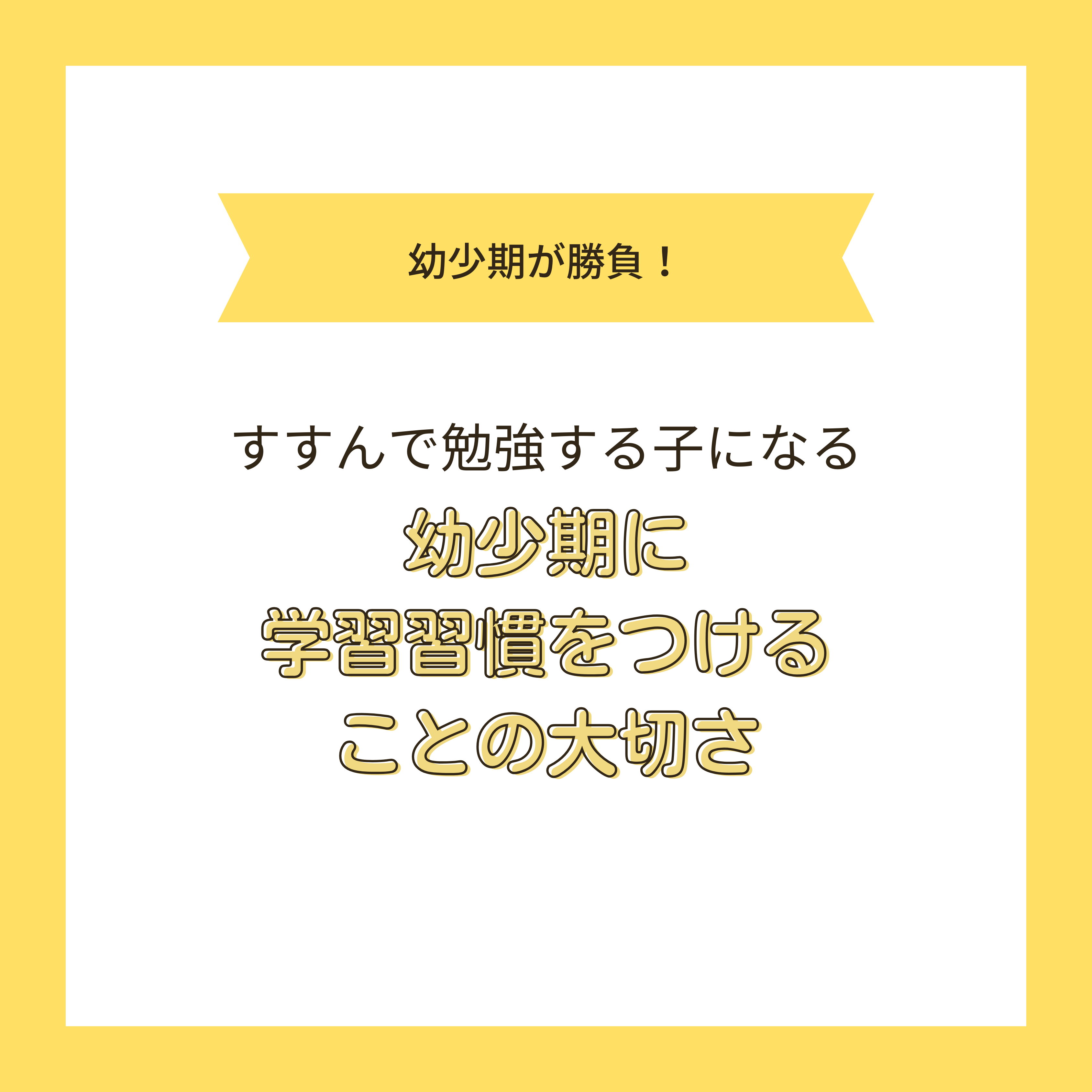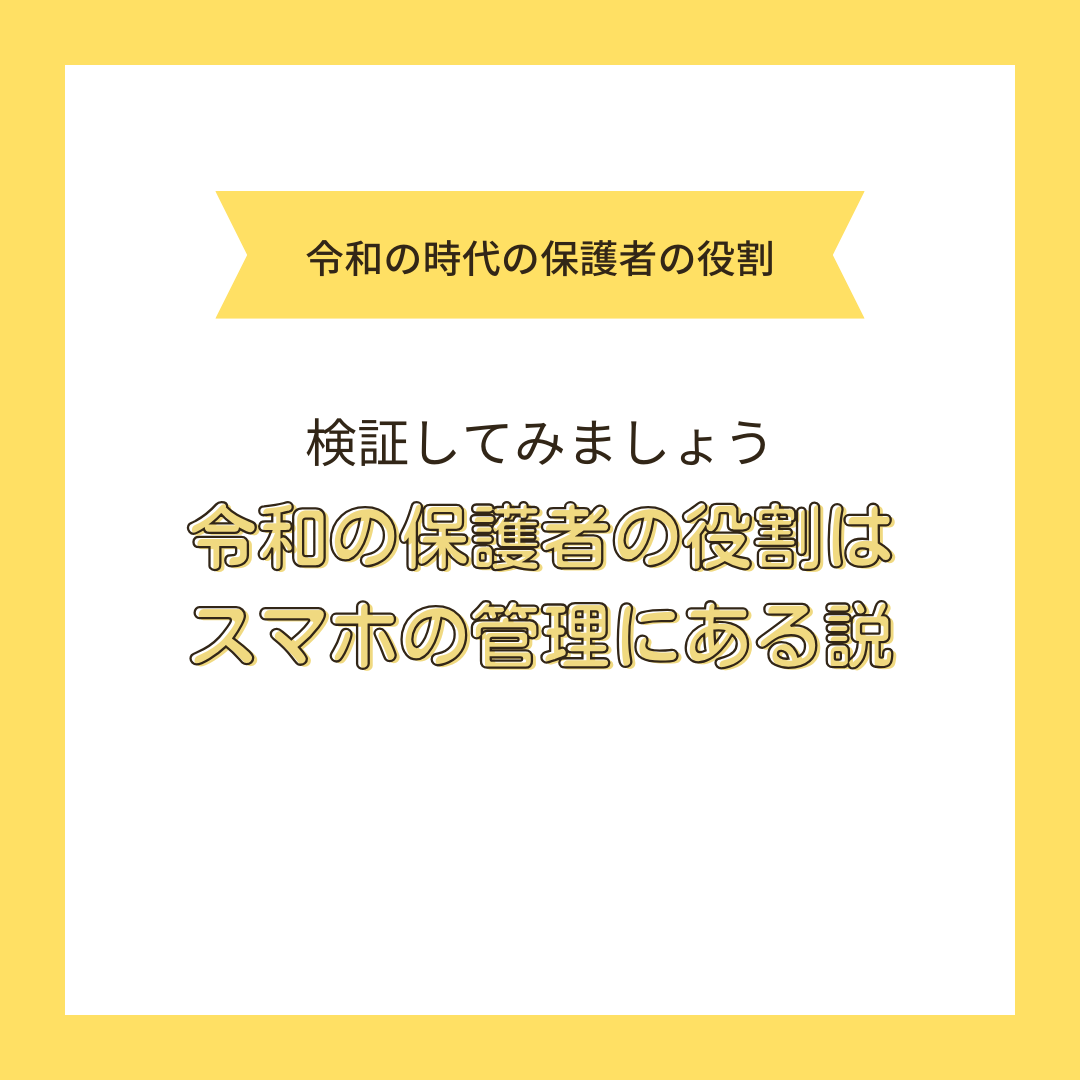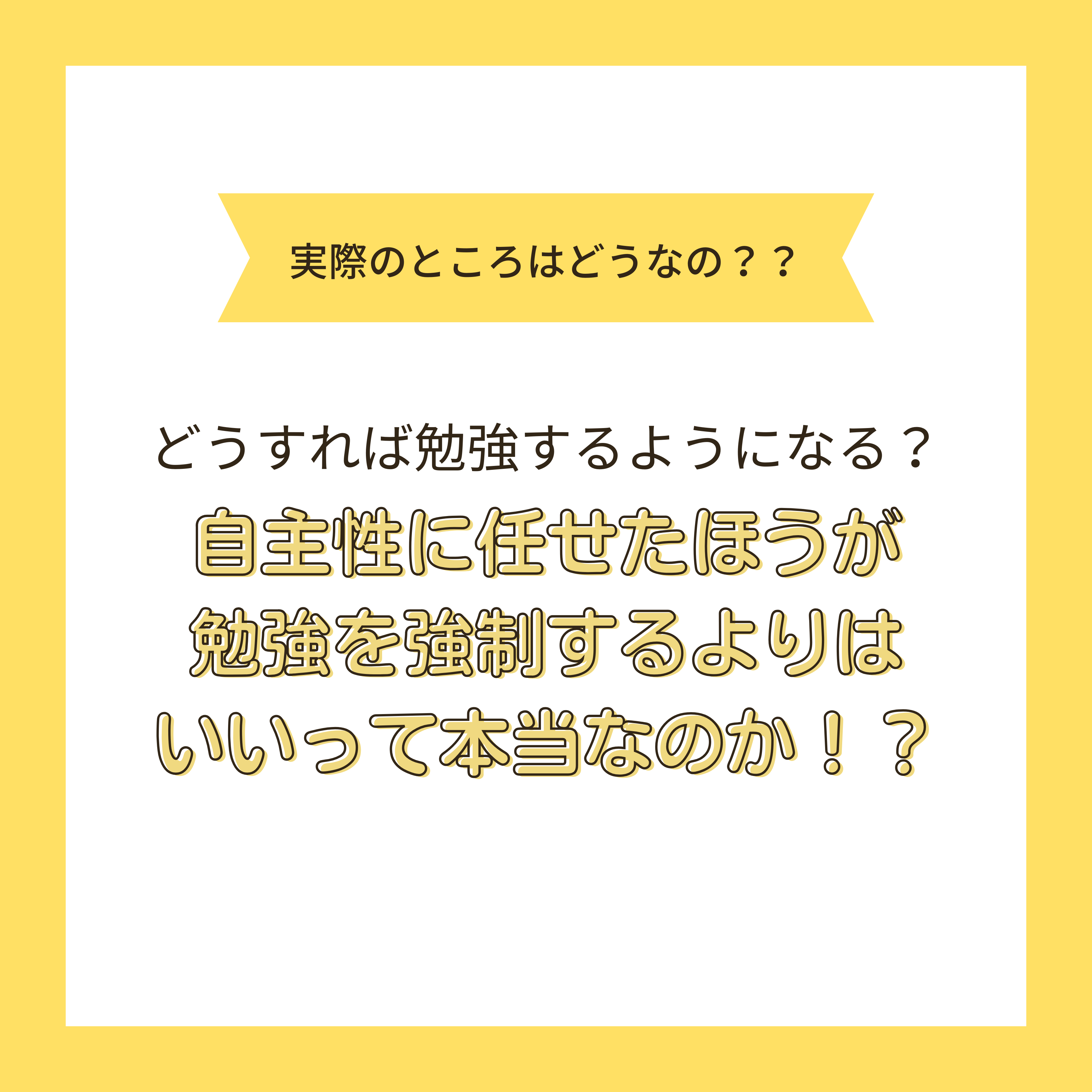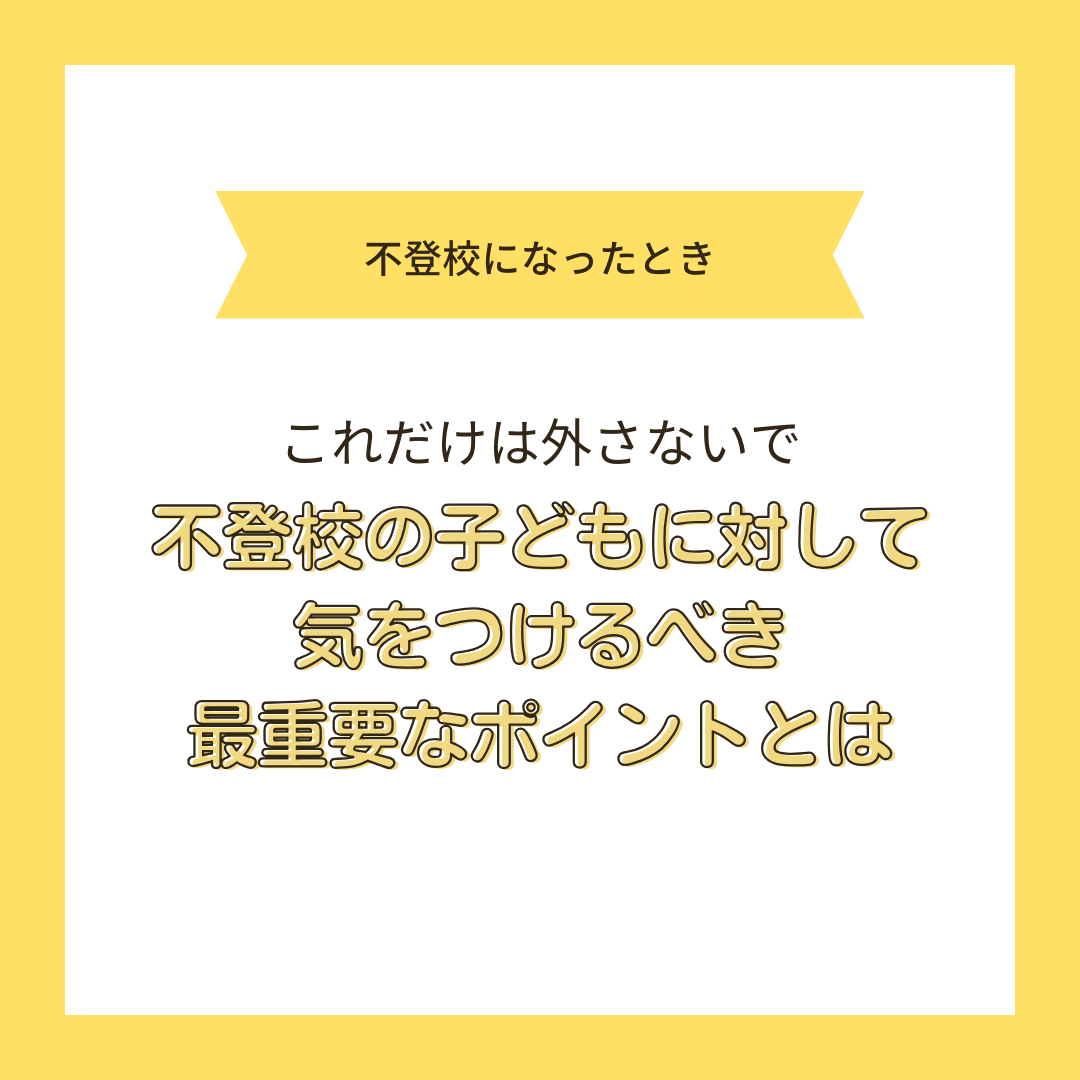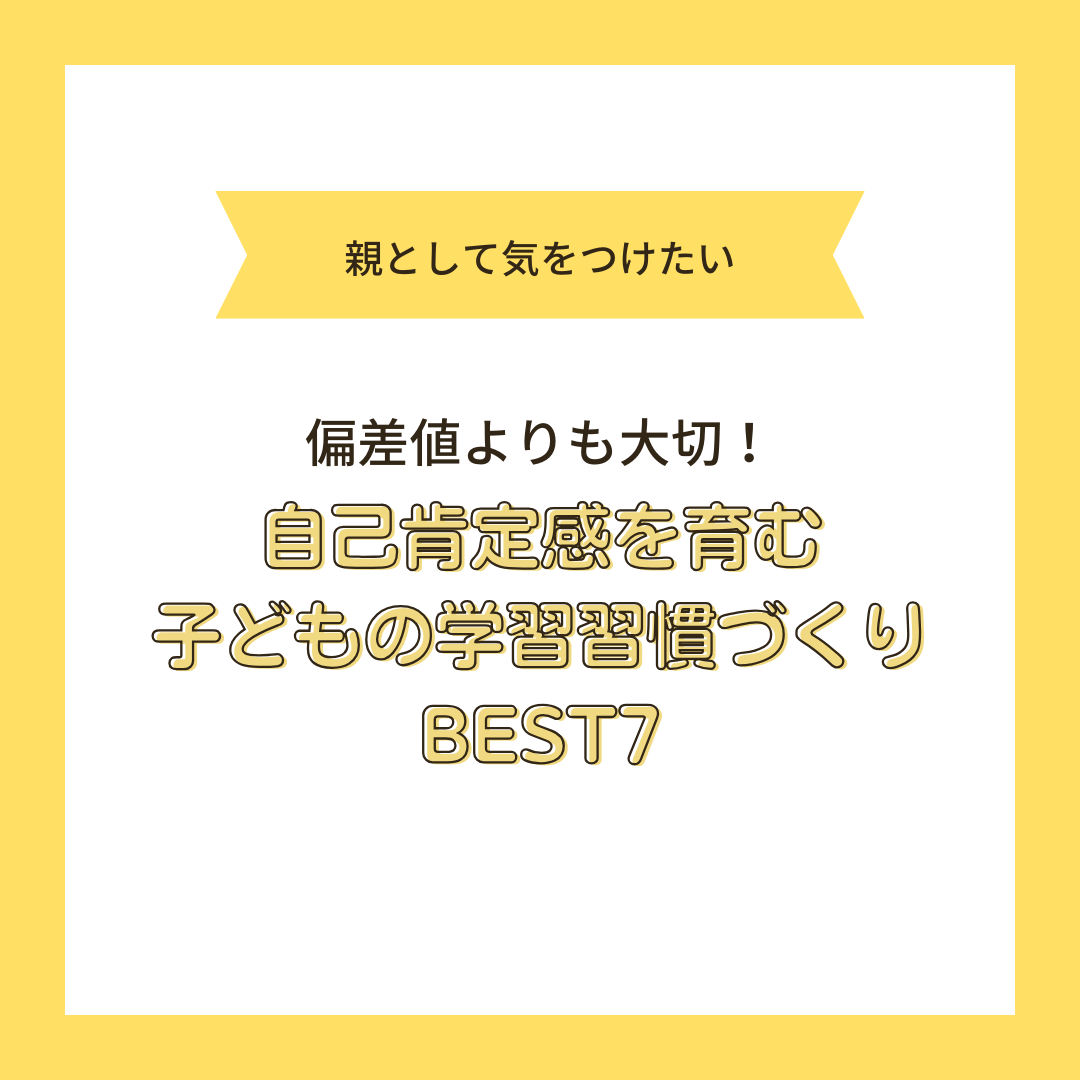こんにちは
自己肯定感を高めるオンライン個別指導塾Cheers!(@cheers.school)です
「うちの子、全然勉強しなくて…」 「『勉強しなさい!』って言うと、部屋に閉じこもっちゃうんです」
塾を運営していると、保護者の皆様からこんなお悩みを本当によくお聞きします。毎日お仕事や家事で忙しい中、お子様の勉強のことまで気にかけないといけない。その大変さ、本当にお察しします。
今日は、そんな悩める保護者の皆様の心が少しでも軽くなるように、「勉強しなさい!」という言葉を使わなくても、お子様が自分から机に向かうきっかけになるかもしれない、そんな「言葉かけ」のヒントについてお話ししたいと思います。
「やる気を出す方法」が、なぜかうまくいかない現実
世の中には、子どものやる気を引き出すためのテクニックに関する情報が溢れていますよね。
例えば、「まずは5分だけやってみよう!」とハードルを下げてみたり、ゲーム時間を交換条件にした「ご褒美作戦」だったり、「将来の夢のためだよ」と諭してみたり。
これらは全部、立派な方法論です。そして、実際にうまくいくお子様もいるでしょう。
でも、現実はどうでしょうか。
「5分だけって言っても、その5分が始まらないのよ…」 「ご褒美の要求が、だんだんエスカレートしてきて…」 「将来の夢なんてない、って言われたら、もう何も言えません」
こんな風に、理論通りにはいかないのが子育てのリアル、というものかもしれません。頑張って試してみたのにうまくいかないと、「うちの子には効果ないんだ…」「私のやり方が悪いのかな…」なんて、自分を責めてしまう保護者の方も少なくないのではないでしょうか。
なぜ、これらの「正しい」はずの方法がうまくいかないことがあるのでしょうか。
私は、その大きな理由の一つに、お子様の「心のコップ」の状態があると考えています。 これをものすごくざっくりいうと、勉強という行動を起こすためのエネルギーが、そもそも心に溜まっていない状態、という意味です。
心のコップが空っぽでカラカラなのに、「さあ、走りなさい!」と言われても走れないのと同じで、まずはそのコップに潤いを与えてあげることが、実は一番の近道なのかもしれません。
「言いたくない親」と「できない子」のすれ違い
ここで少し、保護者様ご自身の気持ちにも目を向けてみたいと思います。
本当は、「勉強しなさい!」なんて、言いたくて言っているわけではないですよね。
その言葉を口にした後の、あの気まずい空気。お子様の不機嫌な顔や、時には反抗的な態度。そして、そんなやり取りをした後の、ご自身の心に残る罪悪感や自己嫌悪…。
「もっとうまく関わってあげられたら」 「あんな言い方じゃなかったら」
そう思えば思うほど、どうしていいか分からなくなってしまう。そのお気持ち、本当によく分かります。
一方で、お子様自身も、実は苦しんでいるのかもしれません。
「勉強しなきゃいけないのは、わかってる」 「でも、やる気が出ない。体が動かない」
頭では理解しているのに、心がついていかない。そんな自分自身に、お子様もイライラしたり、落ち込んだりしている可能性があります。「勉強しなさい!」という言葉は、その無力感をさらに刺激してしまう「引き金」になっているだけなのかもしれないのです。
この、「言いたくないのに言ってしまう親」と、「やりたいのにできない子」。この悲しいすれ違いこそが、問題の根っこにあるのではないでしょうか。
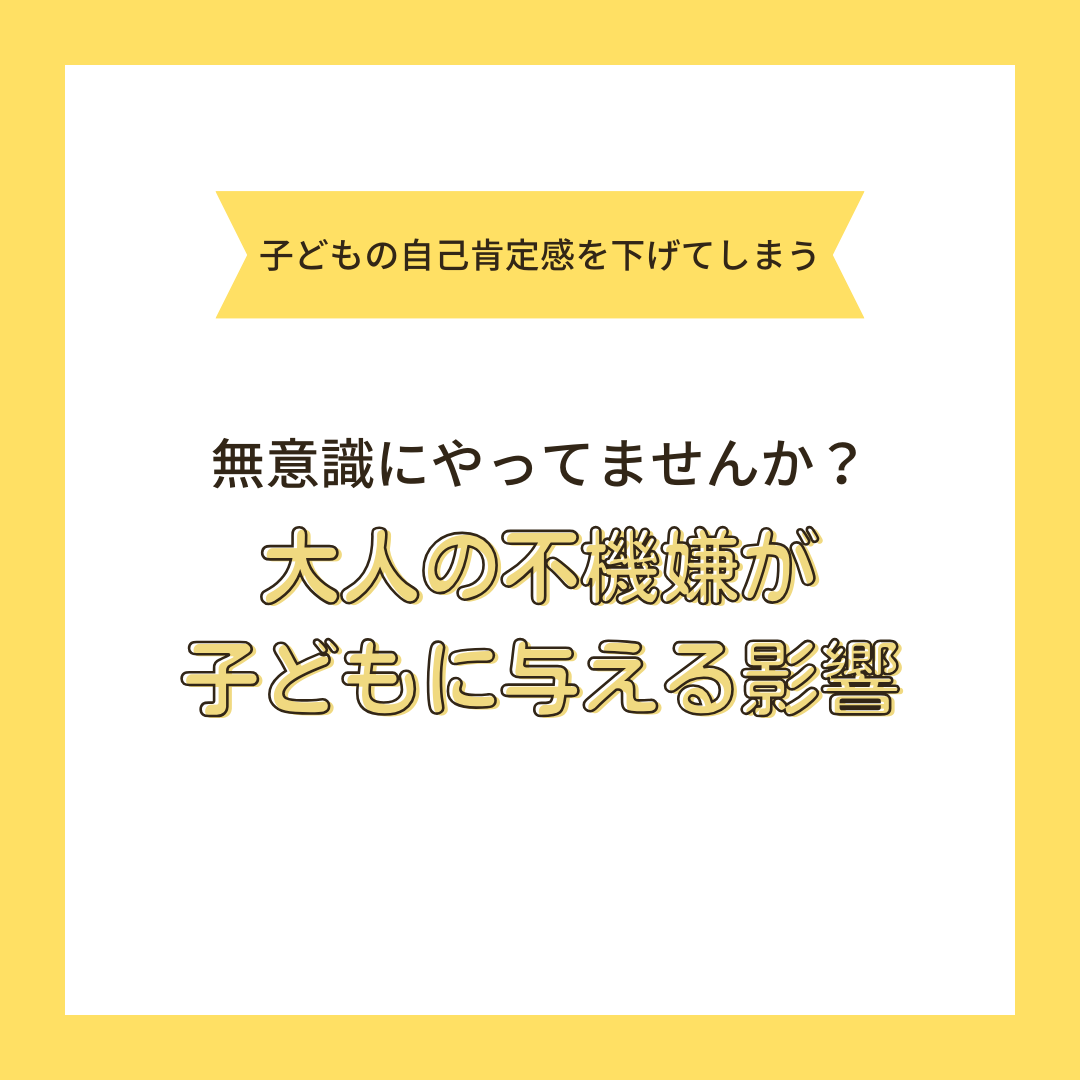
「勉強しなさい!」の代わりになる、心のコップを満たす言葉かけ3選
というわけで、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
お子様の心のコップを少しずつ満たし、自分から動くエネルギーを育むための「言葉かけ」を3つ、具体的な会話例と共にご紹介します。
これは、お子様をコントロールするためのテクニックではありません。あくまで、親子の関係性をより良くし、お子様が安心してエネルギーを蓄えられるような環境を作るためのヒントです。
1. 「存在」をまるごと認める、承認の言葉かけ
まず一番にお伝えしたいのは、勉強という「行動(doing)」ではなく、お子様の「あり方(being)」そのものに目を向けて、それを言葉にしてあげることです。
私たちはつい、子どもが何かを「した」ことに対して、「すごいね!」「えらいね!」と褒めがちです。もちろんそれも大切ですが、そればかりだと、子どもは「何かをしないと自分は認めてもらえないんだ」という考えを無意識に持ってしまいます。
そうではなく、何気ない日常の中で、お子様の状態や存在そのものを認めてあげる言葉をかけてみてください。
【具体的な言葉かけの例】
- (部活から疲れて帰ってきた時に) 「おかえり!今日も練習大変だったね。疲れたでしょ」 (NG例:「疲れてると思うけど、宿題は大丈夫なの?」)
- (特に何もしていなくても、ふとした時に) 「あなたが家にいてくれると、なんだか安心するなあ」 (評価ではなく、ただ親が感じたことを伝える「I(アイ)メッセージ」です)
- (好きなゲームや動画に夢中になっている時に) 「本当に〇〇が好きだね。それだけ夢中になれるものがあるって、すごいことだよ」 (まずは子どもの「好き」を否定せず、受け入れる姿勢を見せます)
【なぜ効果的なのか?】
これらの言葉には、評価や条件がありません。「〇〇ができたら認めてあげる」ではなく、「あなたが、ただそこにいるだけで価値がある」というメッセージが伝わります。
これをものすごくざっくりいうと、「無条件の愛情」を伝えるということです。
心のコップがカラカラのお子様にとって、これ以上嬉しいことはありません。親は自分の味方なんだ、自分はここにいていいんだ、という安心感が、心のコップをゆっくりと満たしていきます。
勉強の話をするのは、その後からでも全く遅くありません。まずは、お子様が安心して羽を休められる「安全基地」を作ってあげる。そんなイメージです。
2. 「自分で決めた」感覚を育む、選択肢の言葉かけ
次に試していただきたいのは、命令ではなく「選択肢」を提示することです。
「勉強しなさい!」は、典型的な命令形の言葉です。心理学的に、人は他人からコントロールされることを嫌い、自分で自分の行動を決めたいという「自己決定感」の欲求を持っています。この欲求が満たされないと、人は反発したくなるのです。これを「心理的リアクタンス」と言ったりします。
なんだか難しい言葉が出てきましたが、要するに「あまのじゃく」な気持ちのことです。言われた通りになんて、やりたくない!という、あのかわいらしくも厄介な感情です。
だからこそ、「やりなさい」ではなく、「どっちがいい?」と問いかけてみてください。
【具体的な言葉かけの例】
- (勉強を始めるきっかけとして) 「お風呂に入る前に5分だけ勉強するのと、お風呂から出た後に15分やるの、どっちがいい?」
- (やるべきことが複数ある時に) 「数学の宿題と、英語の単語暗記、どっちから先に片付けたい?」
- (全く手付かずの時に) 「今日は問題集を2ページ進めるのと、昨日間違えた問題をもう一回解き直すの、どっちならできそう?」
【なぜ効果的なのか?】
たとえ親が提示した選択肢であっても、「自分で選んで決めた」という感覚は、お子様の行動への責任感とモチベーションを高めます。
ポイントは、いきなり大きな選択をさせないことです。「今日の勉強計画を全部自分で立てなさい」と言われても、エネルギーのないお子様には荷が重すぎます。
「AかBか」という、具体的で、どちらを選んでも少しは前に進めるような、小さな小さな選択肢を提示してあげる。そうやって、「自分で選んで、行動できた」という小さな成功体験を積ませてあげることが大切です。
これは、お子様の「自己決定感」という、心のコップを満たすための重要な蛇口を開けてあげるような作業です。
\この記事が気になった保護者さまへ/
オンライン個別指導塾 Cheers! で
無料体験授業 を受けませんか?
- ビジネスオーナー歴28年・元よしもとNSC芸人
塾長かつ師匠が直接伴走 - 平均36点アップの定期テスト対策/教科書準拠の学習
- Zoom+Slackで「質問→即回答」課題も即日添削
✅ 13,500円/週2回・19,500円/週3回(税抜)の圧倒的低料金
✅ 小5〜中3なら学年・不登校状況を問いません
※体験後の営業電話は一切ありませんので安心してお試しください
3. 「一緒にやろう」という姿勢を見せる、仲間意識の言葉かけ
最後のヒントは、お子様を一人で戦わせない、ということです。
勉強は孤独な作業です。特に、わからない問題にぶつかった時、周りのみんなはできているように見える時、その孤独感は一層強まります。
そんな時、親が「監督」や「審判」のような立ち位置から「やりなさい!」と指示するのではなく、「チームメイト」として同じ方向を向いてあげるような言葉かけが、お子様の心を軽くすることがあります。
【具体的な言葉かけの例】
- (リビングで勉強しているお子様の隣で) 「お母さんも読書するから、一緒に頑張ろうか」 (スマホをいじりながら「勉強しなさい」と言うのとは、伝わるメッセージが全く違います)
- (テレビのニュースを見ながら) 「最近よくSDGsって聞くけど、これってどういうことなんだろうね?学校で習った?お父さんもちょっと調べてみるよ」
- (お子様が苦手な科目について) 「お母さんも英語は苦手だったなあ。今でも海外ドラマは字幕がないと全然わからないよ。でも、この単語は知ってる!」
【なぜ効果的なのか?
親が勉強や新しい知識に対してオープンな姿勢を見せることで、お子様は「勉強=子どもが我慢してやらされること」というイメージから、「勉強=大人も楽しんだり、必要としたりするもの」というイメージへと、少しずつ認識を変えていくことができます。
完璧な親である必要は全くありません。むしろ、「お父さんもわからない」「お母さんも苦手だった」と弱みを見せることで、お子様は「自分だけじゃないんだ」と安心し、親近感を覚えます。
勉強という大変な課題に、一緒に取り組んでくれる「仲間」がいる。その感覚が、孤独感を和らげ、もう一歩踏み出すための勇気を与えてくれるのです。
まとめ
とはいえ、毎日これらの言葉かけを完璧に実践するのは、本当に大変なことだと思います。
仕事で疲れて帰ってきた日に、子どもの存在を承認する余裕なんてない時もあるでしょう。何度も選択肢を提示したのに、子どもが「どっちも嫌だ!」と答える日もあるはずです。
それでいいんです。うまくいかなくて当たり前です。保護者の皆様も、どうかご自身を責めないでください。
というわけで、今日お話ししたかったことの結論は、**「子どもを無理やり変えようとするのではなく、親子のコミュニケーションの『型』を少しだけ変えてみませんか?」**というご提案です。
「勉強しなさい!」というコントロールの言葉から、「疲れてるね」という承認の言葉へ。「やりなさい」という命令から、「どっちがいい?」という質問へ。「監督」から「チームメイト」へ。
この小さな変化が、お子様の心のコップを少しずつ満たし、親子関係という土壌を豊かにしていきます。すぐに勉強時間が増えなくても、お子様の表情が和らいだり、会話が増えたりしたら、それは大きな大きな一歩です。
そして、どうしても家庭内での関わりだけでは難しい、第三者の専門的なサポートが必要だと感じた時には、いつでも私たちのような存在を頼ってください。
記事を最後まで読んでいただきありがとうございました
オンライン個別指導塾Cheers!では、経験豊富で愛のある塾長が、一人ひとりの良いところを認めてあげて褒めながら、お子様の学力を伸ばしていくオンライン個別指導塾です
無料体験授業のご希望・子育てやお子様の学業に関する悩みやご相談など無料で承ります
いつでもお気軽にご相談ください!
無料相談はこちらまで→cheers-school.com/