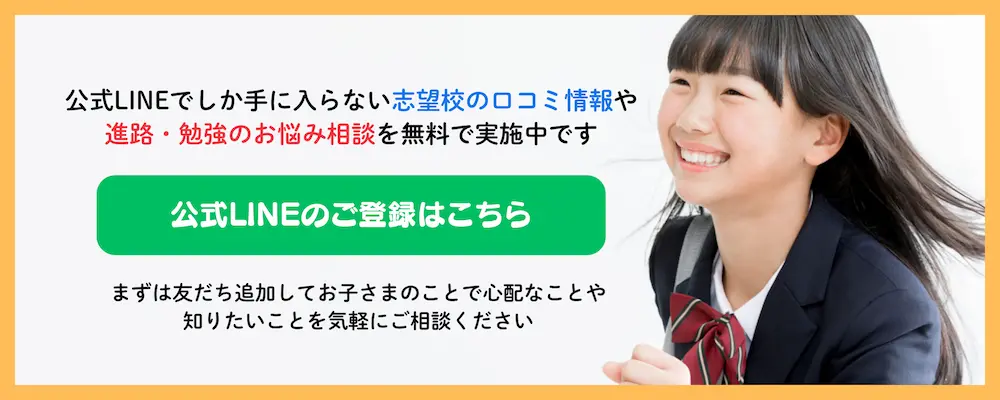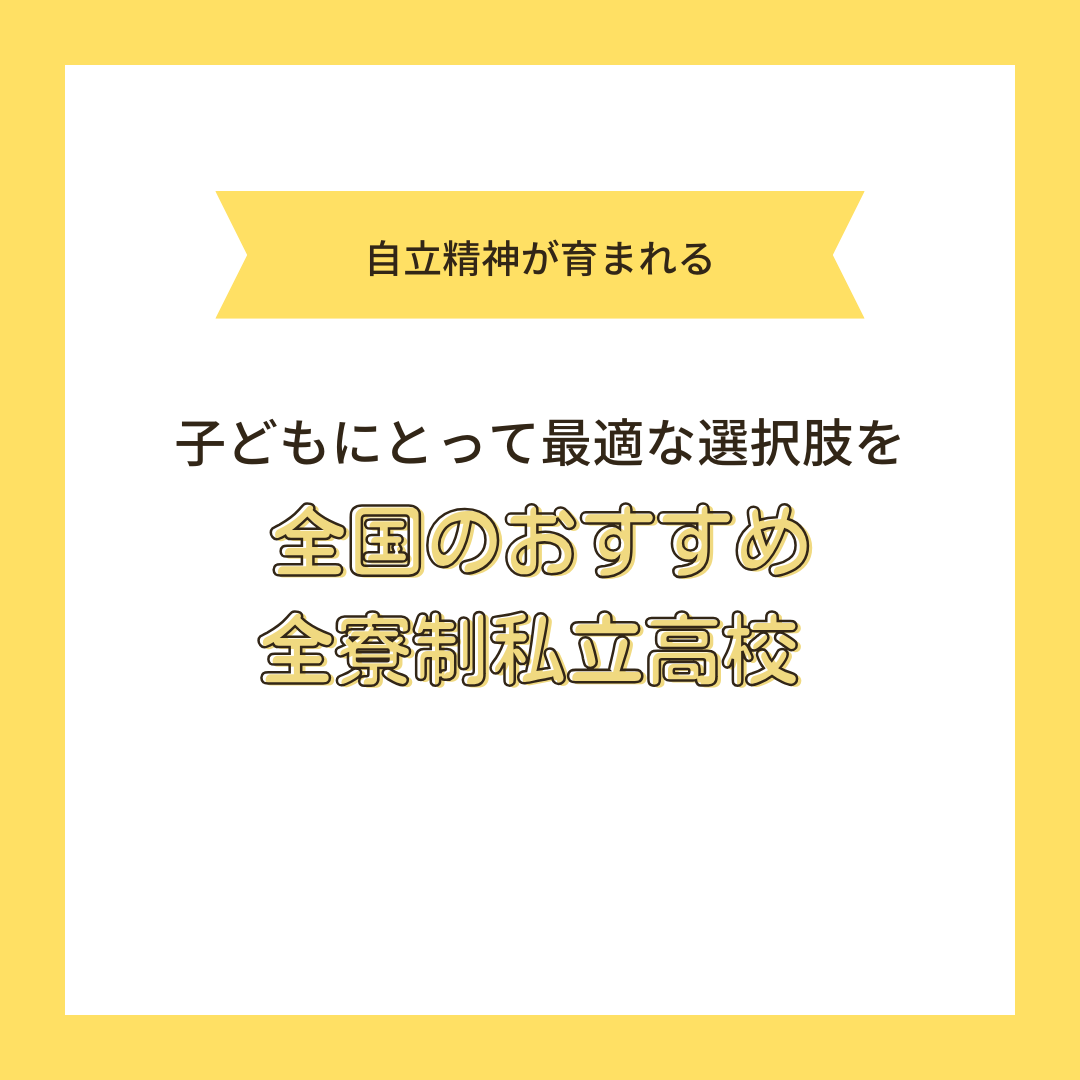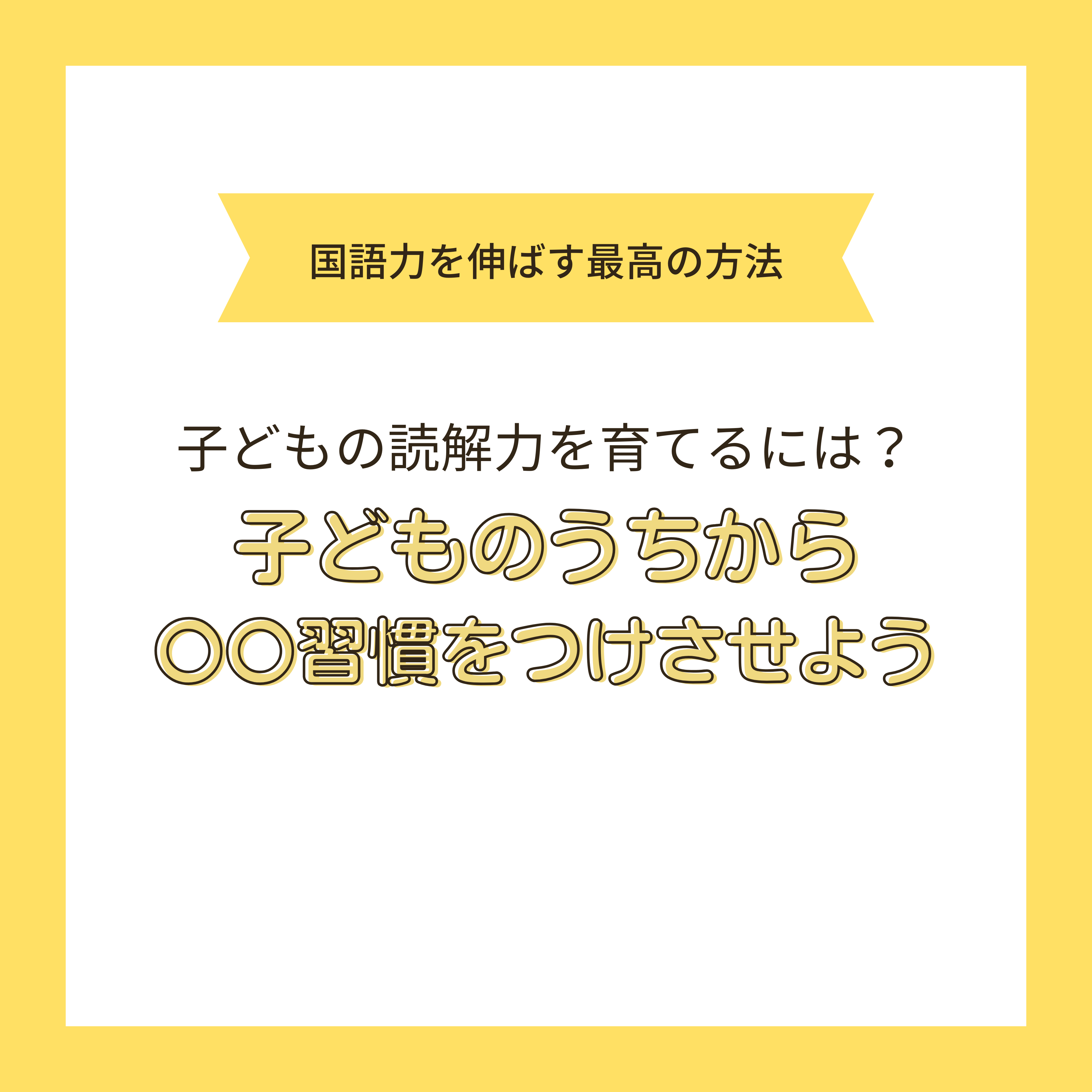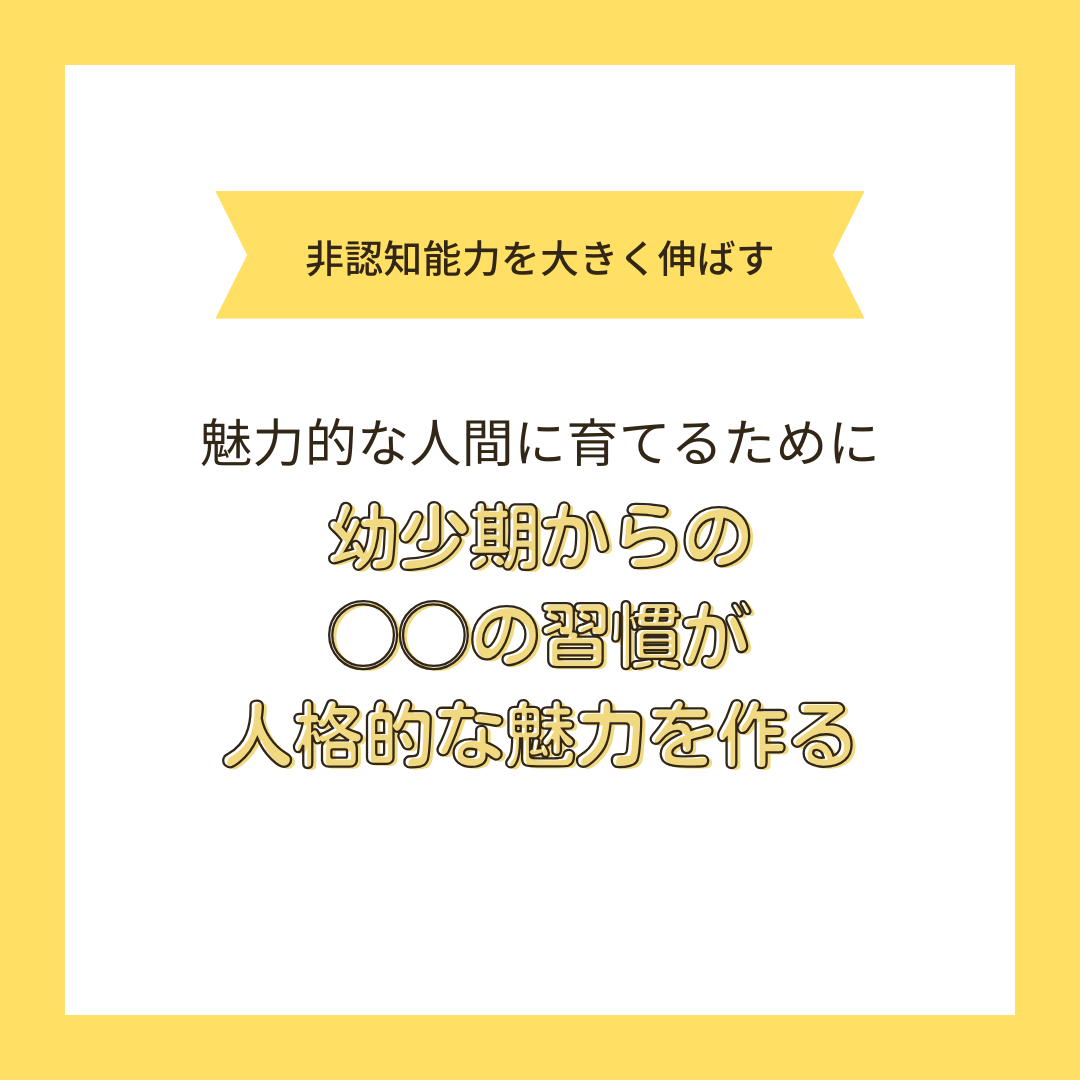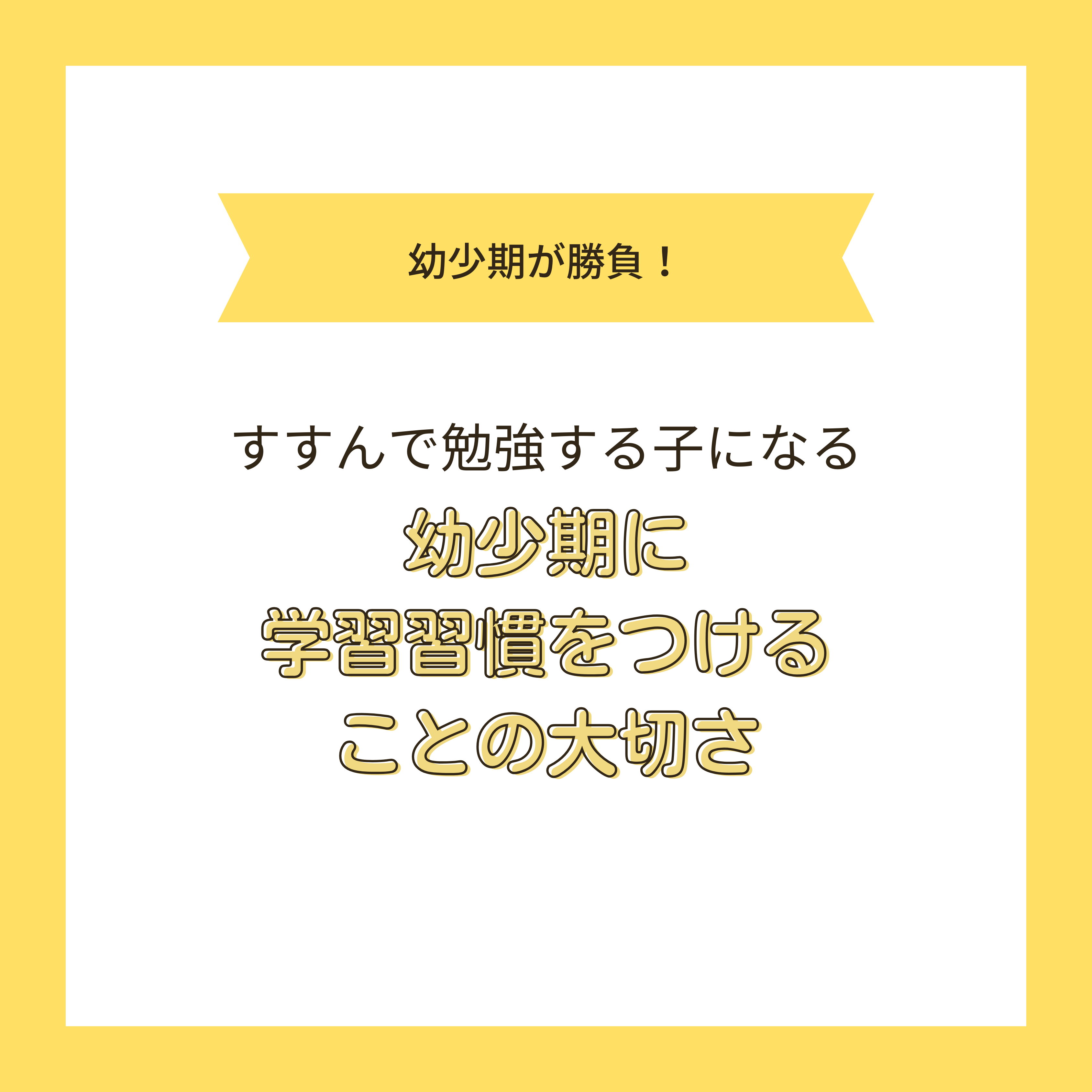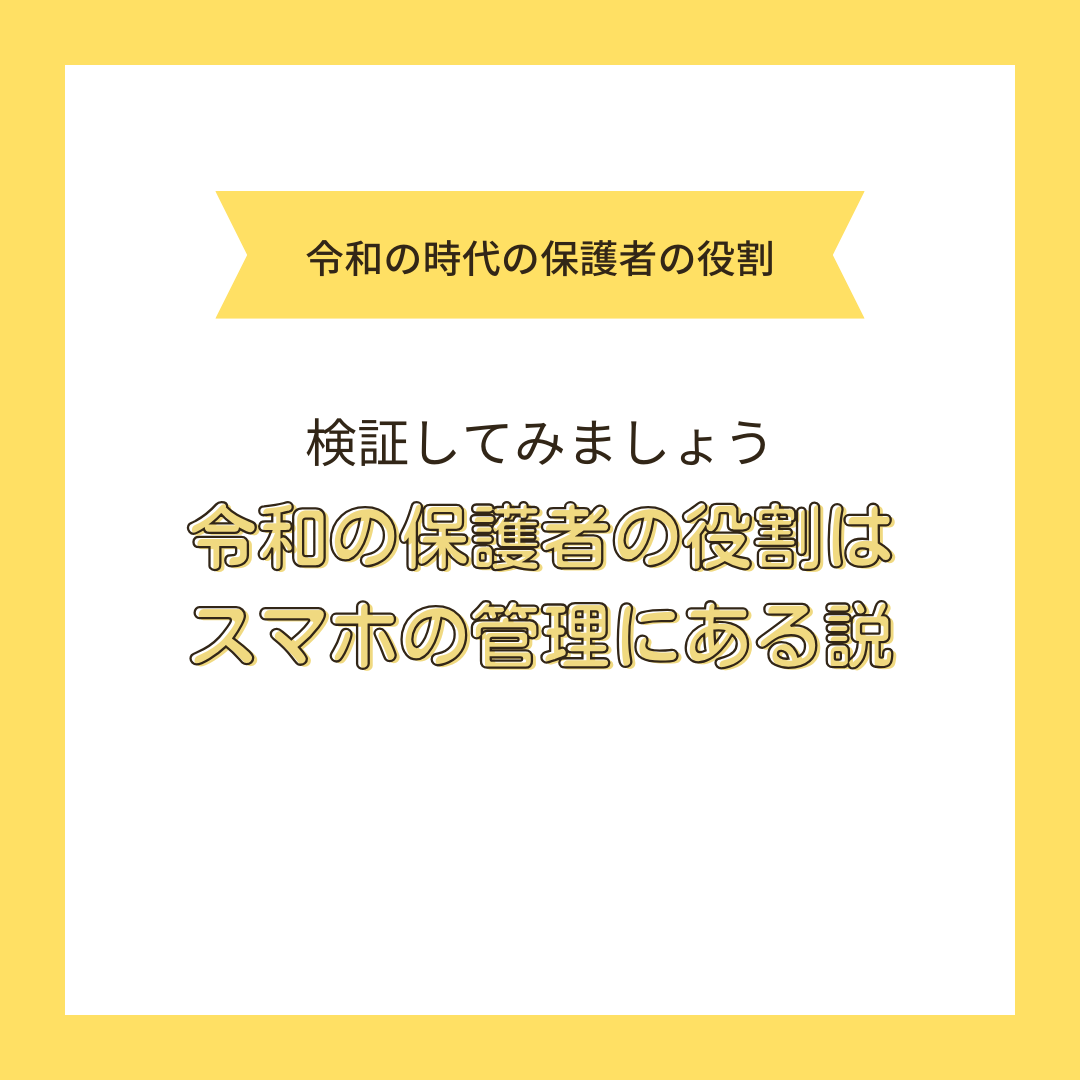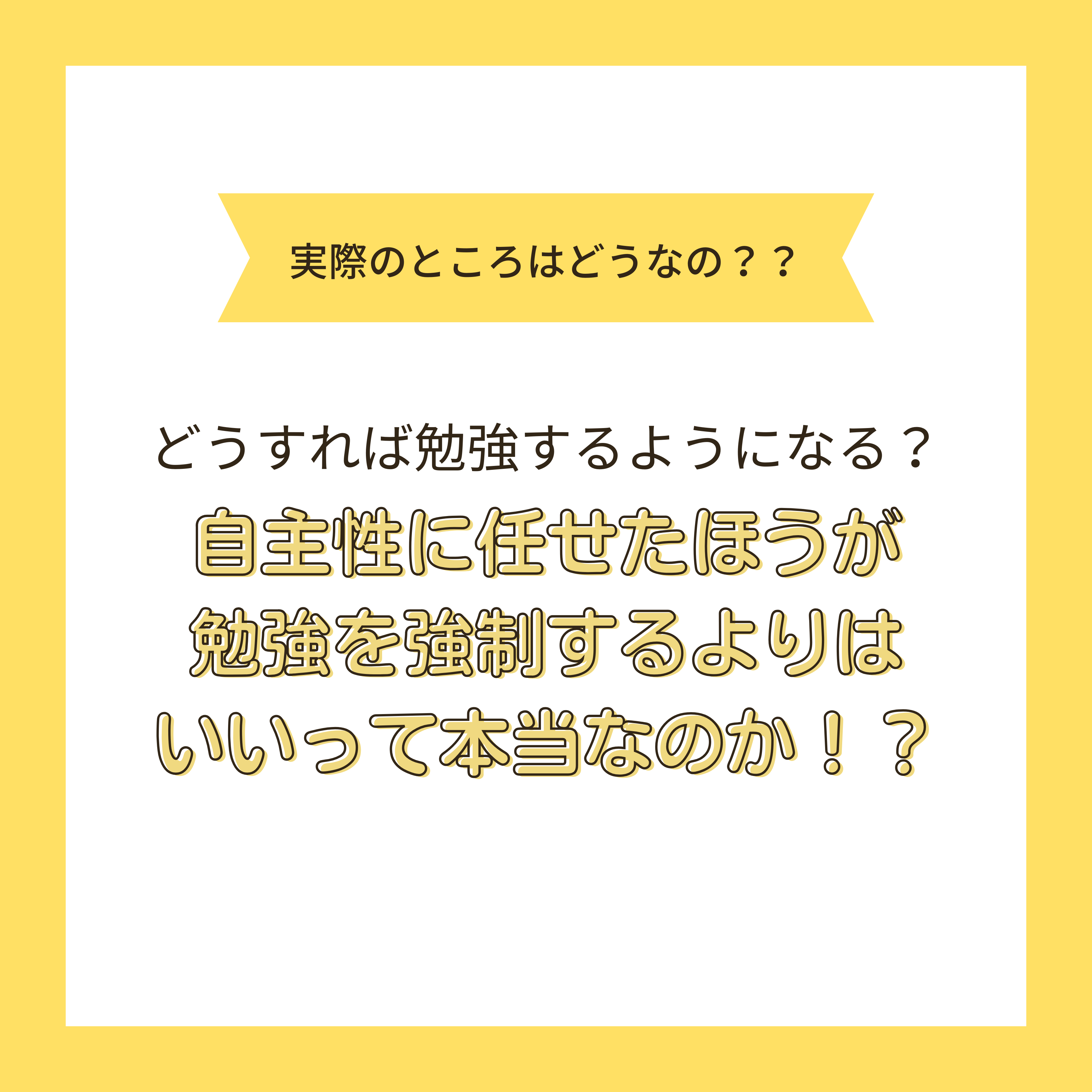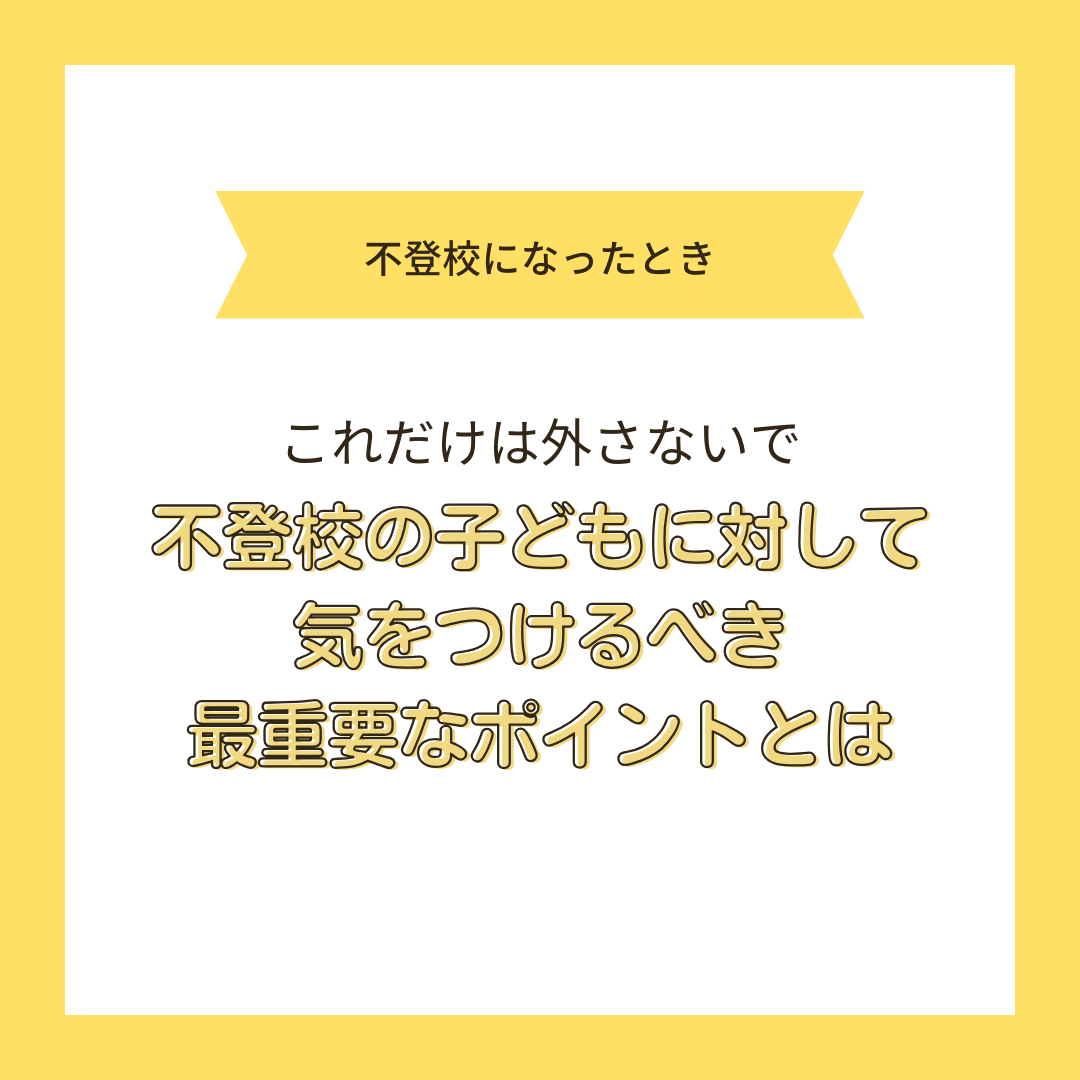こんにちは!
自己肯定感を高めるオンライン個別指導塾Cheers!(@cheers.school)です。
「うちの子、なんだか自信がなさそう…」
「最近、何を考えているのか分からない…反抗期かしら?」
「子どものやる気を引き出すには、どう関わればいいんだろう?」
思春期真っ只中の中学生のお子様との関わり方に、日々悩んだり、戸惑ったりしている保護者の皆様、こんにちは。心も体も大きく変化するこの時期、お子様との距離感やコミュニケーションの取り方に難しさを感じるのは、決してあなただけではありません。
特に、勉強や部活、友人関係など、様々な場面で壁にぶつかったり、他人と比較して落ち込んだりしやすい中学生にとって、「自己肯定感」、つまり「ありのままの自分を大切に思い、価値ある存在だと受け入れる感覚」を育むことは、非常に重要です。自己肯定感は、困難に立ち向かう力、新しいことに挑戦する意欲、そして自分らしい人生を歩むための土台となるからです。
私たちオンライン個別指導塾Cheers!は、「褒めて伸ばす」ことを教育方針の一つとして大切にしています。しかし、それは単に「すごいね!」「えらいね!」と結果だけを褒めることではありません。お子様一人ひとりの努力のプロセスに目を向け、具体的な頑張りを認め、心からの言葉で伝えること。そして、他人と比べるのではなく、その子自身の成長を喜ぶこと。そういった関わりを通して、お子様の内面から湧き出るような、本物の自信(自己肯定感)を育むことを目指しています。
「でも、具体的にどうすればいいの?」
そう思われる保護者の皆様のために、この記事では、「褒める」という言葉だけにとらわれず、中学生のお子様の自己肯定感を効果的に育むための具体的な関わり方を、すぐに実践できる10個のヒントとしてご紹介します。心理学的な視点も少し交えながら、今日からできるアクションをお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ、ただ「褒める」だけでは足りないの? 思春期の心と自己肯定感
まず、「なぜ、ただ褒めるだけでは不十分なのか?」という点から考えてみましょう。
もちろん、褒められること自体は嬉しいものです。しかし、特に思春期の中学生に対して、表面的な褒め言葉だけを繰り返していると、逆効果になってしまう可能性すらあります。
- 「結果」ばかり褒められると…: 「良い結果を出さないと認めてもらえない」「失敗したら価値がない」と感じてしまい、挑戦を恐れたり、プレッシャーに苦しんだりする原因になります。
- 具体性のない褒め言葉は…: 「すごいね」「頑張ったね」だけでは、子どもは何を評価されているのか分からず、「本当はそう思っていないのでは?」と疑心暗鬼になったり、心に響かなかったりします。
- 他人との比較で褒められると…: 「〇〇ちゃんよりできて偉いね」といった褒め方は、一時的な優越感は与えるかもしれませんが、「常に誰かと比較される」「勝たないと意味がない」という価値観を植え付け、他人の評価に依存する心を育ててしまいます。
本当の自己肯定感とは、「何かができるから自分はOK」なのではなく、「できてもできなくても、ありのままの自分でいいんだ」と思える感覚です。この感覚を育むためには、結果や能力といった外面的な評価だけでなく、お子様の内面、つまり努力、感情、考え方、そして存在そのものに目を向け、受け止め、認めていく関わりが不可欠なのです。
それでは、具体的にどのような関わり方が有効なのか、10個のヒントを見ていきましょう。
【実践編】子どもの自己肯定感をグングン伸ばす!具体的な関わり方10選
1. 結果よりも「プロセス(過程)」を具体的に認める
テストの点数や試合の結果など、「できたこと」だけを評価するのではなく、そこに至るまでの「頑張り」や「工夫」に注目し、具体的に言葉にして伝えましょう。
- なぜ有効?: 結果は運や状況に左右されることもありますが、努力や工夫は本人の意志と行動の表れです。プロセスを認められることで、子どもは「自分の頑張りは無駄じゃなかったんだ」「次も頑張ろう」という内発的動機づけ(やらされ感ではなく、自らやりたいと思う気持ち)を高めます。これは心理学でいう「自己効力感(自分ならできると思える感覚)」にも繋がります。
- 具体的な声かけ例:
- 「テストの点、目標まであと一歩だったけど、毎日コツコツ勉強してたの、ちゃんと見てたよ。あの難しい問題にも諦めずに取り組んでたね。」
- 「試合には負けちゃったけど、最後まで諦めずにボールを追いかけてた姿、すごくかっこよかったよ。練習でやった〇〇、試合で試せてたね!」
- 「このレポート、完成させるの大変だったでしょ? 資料をたくさん調べて、自分の言葉でまとめようと頑張ってたね。」
- 実践のコツ: 日頃から子どもの様子をよく観察し、「具体的に」どこをどう頑張っていたのかを伝えることがポイントです。「頑張ったね」だけでなく、「〇〇を頑張ったね」と具体的に!
2. 「できたこと」より「成長したこと」に注目する(過去の自分との比較)
「前はできなかったのに、できるようになったね!」「〇〇がすごく上達したね!」というように、過去のその子自身と比べて、どれだけ成長したかを伝えましょう。
- なぜ有効?: 他人と比較されることなく、自分自身の成長を実感できるため、純粋な達成感と自信につながります。「自分は成長できる存在なんだ」という感覚は、自己肯定感の重要な要素です。
- 具体的な声かけ例:
- 「前はこの計算問題、時間かかってたけど、すごく速く正確にできるようになったね!練習の成果だね。」
- 「初めて〇〇に挑戦した時は不安そうだったけど、今は堂々とできるようになったね。すごい成長だよ!」
- 「以前は自分の意見を言うのが苦手だったけど、今日はしっかり自分の考えを伝えられていたね。」
- 実践のコツ: 子どもの過去の姿を覚えておき、「ビフォーアフター」を具体的に示すと、子ども自身も成長を実感しやすくなります。小さな変化も見逃さないようにしましょう。
3. 子どもの「感情」に寄り添い、受け止める(共感・傾聴)
嬉しい時、悲しい時、悔しい時、腹が立つ時… 子どもが示す様々な感情を否定せず、「そう感じているんだね」と、まずは受け止め、共感する姿勢を示しましょう。
- なぜ有効?: 自分の感情を安心して表現でき、それを受け止めてもらえる経験は、「自分は理解されている」「ここに居ていいんだ」という安心感と自己肯定感の基盤を築きます。特に思春期は感情の起伏が激しくなりがちなので、寄り添う姿勢が大切です。
- 具体的な声かけ例:
- (落ち込んでいる時)「そっか、そんなことがあって悔しかったんだね。つらかったね。」(アドバイスは後回し!)
- (怒っている時)「〇〇なことがあって、すごく腹が立ったんだね。」(まずは感情を受け止める)
- (喜んでいる時)「やったね!すごく嬉しいんだね!私も嬉しいよ!」(一緒に喜ぶ)
- 実践のコツ: すぐにアドバイスや評価をしようとせず、まずは子どもの言葉に耳を傾け(傾聴)、感情を言葉にして返す(共感)ことを意識しましょう。「でも」「だって」と否定しないことが大切です。
4. 失敗は「ダメ」じゃなく「学びのチャンス」と捉える声かけ
失敗や間違いを責めるのではなく、「そこから何を学べるか」「次はどうすればいいか」を一緒に考える機会と捉えましょう。
- なぜ有効?: 失敗を過度に恐れることなく、挑戦する意欲を育みます。「失敗しても大丈夫」「失敗から学べばいい」という経験は、困難に立ち向かう力(レジリエンス)を高め、結果的に自己肯定感を支えます。
- 具体的な声かけ例:
- 「今回はうまくいかなかったけど、この経験から何か学べたことはあるかな?」
- 「どこが難しかった? 次に活かせそうなことは何だろう?」
- 「失敗は成功のもとって言うしね!次はこうしてみたらどうかな?」
- 「誰だって失敗することはあるよ。大切なのは、そこからどうするかだよ。」
- 実践のコツ: 感情的に責めるのではなく、冷静に状況を振り返り、前向きな視点を提供することを心がけましょう。保護者自身が失敗を恐れない姿勢を見せることも大切です。
5. 子ども自身の「考え」や「意見」を尊重する(自己決定の機会)
進路のこと、友達とのこと、日々の選択… 様々な場面で、子どもの考えや意見に耳を傾け、頭ごなしに否定せず、尊重する姿勢を示しましょう。可能な範囲で、子ども自身に決めさせる機会(自己決定)を与えましょう。
- なぜ有効?: 自分の考えが尊重される経験は、「自分は一人の人間として認められている」という感覚を育みます。また、自分で考えて決めたことは、責任感や主体性(内発的動機づけ)につながり、たとえ結果が伴わなくても納得感を得やすくなります。
- 具体的な関わり方例:
- 「あなたはどうしたい?どう思う?」と問いかける。
- 子どもの意見を最後まで聞き、「なるほど、そういう考えもあるね」と一旦受け止める。
- すぐに答えを教えるのではなく、「どうしたらいいと思う?」と一緒に考える。
- 服選びや休日の過ごし方など、小さなことから自分で決める機会を作る。
- 実践のコツ: 保護者の価値観を押し付けず、子どもの意見を尊重する姿勢が大切です。ただし、安全に関わることや社会のルールから逸脱する場合は、理由を説明し、適切な方向に導く必要はあります。
6. 「ありがとう」「助かるよ」感謝の気持ちを伝える
子どもが何か手伝ってくれた時、気遣ってくれた時、些細なことでも「ありがとう」「助かるよ」と具体的に感謝の気持ちを伝えましょう。
- なぜ有効?: 自分が誰かの役に立っている、必要とされているという実感(自己有用感)は、自己肯定感を高める上で非常に重要です。「自分は家族の一員として貢献できている」と感じることで、自分の存在価値を肯定的に捉えられます。
- 具体的な声かけ例:
- 「お皿洗い手伝ってくれてありがとう!すごく助かったよ。」
- 「疲れてる時に、優しい言葉をかけてくれて嬉しかったよ。ありがとうね。」
- 「〇〇がいてくれると、家が明るくなるよ。いつもありがとう。」
- 実践のコツ: やってもらって当たり前と思わず、小さなことにも意識的に感謝を伝えましょう。具体的に「何が」助かったのかを伝えると、より効果的です。
7. 「あなたがいるだけで嬉しい」存在そのものを肯定する
テストの点数や成績、何かができる・できないに関わらず、「あなたがあなたでいるだけで価値がある」「生まれてきてくれてありがとう」という、存在そのものを肯定するメッセージを伝えましょう。
- なぜ有効?: これが自己肯定感の根幹となる「無条件の肯定的関心」です。親から無条件に愛され、受け入れられているという感覚は、子どもにとって最大の心の安全基地となり、何があっても揺るがない自己肯定感の土台を築きます。
- 具体的な伝え方例:
- 言葉で直接伝える:「大好きだよ」「あなたがいてくれるだけで幸せだよ」「生まれてきてくれてありがとう」
- スキンシップ:ハグをする、頭をなでる(※思春期は嫌がる場合もあるので、様子を見ながら)
- 誕生日や節目に、存在への感謝を伝える手紙を書く。
- 日常の中で、笑顔で目を合わせて話す。
- 実践のコツ: 改まって伝えるのが照れくさい場合は、日常のふとした瞬間に、態度や表情で示すだけでも伝わります。大切なのは、条件付きではない、ありのままの存在を肯定する気持ちです。
8. 小さな「できた!」を一緒に喜ぶ
以前はできなかったことが少しできるようになった、苦手なことに挑戦してみた、など、どんなに小さな「できた!」でも見逃さず、一緒に喜び、その達成感を共有しましょう。
- なぜ有効?: 小さな成功体験の積み重ねは、「やればできる!」という自己効力感を着実に育みます。保護者が一緒に喜んでくれることで、その喜びは倍増し、次の挑戦への意欲につながります。
- 具体的な声かけ例:
- 「見て!前より字がきれいになったね!練習した甲斐があったね、やったー!」
- 「苦手な〇〇、今日は最後まで頑張れたんだね!すごいじゃん!」
- 「自分で調べてここまでできたの?素晴らしいね!一緒に喜びたい!」
- 実践のコツ: 結果の大小に関わらず、「できた」という事実そのものを認め、喜びを分かち合うことが大切です。大げさなくらいに喜んであげるのも良いかもしれません。
9. 他人と「比べない」
「〇〇ちゃんはもっとできるのに」「お兄ちゃんはもっと早くできた」など、兄弟姉妹や友達など、他の子どもと比較する言葉は絶対に避けましょう。
- なぜ有効?: 他人と比較されることは、子どもの劣等感を刺激し、自己肯定感を著しく低下させる原因となります。「自分はダメなんだ」と思い込ませてしまい、やる気や自信を奪ってしまいます。比べるなら、過去のその子自身と比べましょう(ヒント2参照)。
- 避けるべき言葉の例:
- 「〇〇くんはもう△△できるんだって。」
- 「なんであなたはできないの?」
- 「お姉ちゃんを見習いなさい。」
- 実践のコツ: 無意識のうちに比較してしまわないよう、常に意識することが大切です。もし比較しそうになったら、「いけない、いけない」と心の中でブレーキをかけましょう。その子の良いところ、頑張っているところに目を向けるようにします。
10. 「信じているよ」という期待を伝える(ピグマリオン効果)
「あなたならできると信じているよ」「きっと乗り越えられるよ」というように、子どもの可能性を信じ、前向きな期待を伝えましょう。
- なぜ有効?: 人は他者から期待されると、その期待に応えようと努力し、実際に成果を上げやすくなるという心理効果があります(ピグマリオン効果)。保護者からの信頼と期待は、子どもにとって大きな力となり、「自分にはできるんだ」という自己効力感と自己肯定感を育みます。
- 具体的な声かけ例:
- 「難しい挑戦だけど、あなたならきっとやり遂げられると信じているよ。」
- 「今は大変かもしれないけど、あなたは乗り越える力を持っているよ。」
- 「あなたの力を信じているから、安心して挑戦しておいで。」
- 実践のコツ: 過度なプレッシャーにならないよう、あくまで「可能性を信じている」という温かいメッセージとして伝えることが大切です。結果を強制するのではなく、プロセスを応援する姿勢で伝えましょう。
関わる上で大切にしたいこと
これらの10個の関わり方を実践する上で、いくつか心に留めておきたいことがあります。
- 心からの言葉で: 上辺だけ、テクニックとして声かけをしても、子どもには見透かされてしまいます。心からそう思って伝えることが何より大切です。
- 一貫性を持つ: 時と場合によって言うことが変わると、子どもは混乱してしまいます。できる範囲で、一貫した態度で関わることを目指しましょう。
- 焦らない、比べない: 自己肯定感は一朝一夕に育つものではありません。他の子と比べず、お子様のペースに合わせて、焦らず、根気強く関わっていくことが大切です。
- 保護者自身の心の余裕も大切: 保護者自身が疲れていたり、ストレスを抱えていたりすると、子どもに温かく関わるのは難しくなります。時には休息を取り、自分自身のケアも忘れないでくださいね。
オンライン個別指導塾Cheers!の取り組み:自己肯定感を育む学びの場
私たちオンライン個別指導塾Cheers!は、これまでお伝えしてきたような考え方に基づき、お子様の自己肯定感を育むことを学習指導の根幹に置いています。
単に勉強を教えるだけでなく、
- 一人ひとりの頑張りや成長を具体的に認め、言葉で伝えること
- 結果だけでなく、そこに至るプロセスを大切にすること
- 失敗を恐れず挑戦できるような、安心できる雰囲気を作ること
- 生徒自身の「考えたい」「学びたい」という気持ちを引き出すこと
を常に心がけています。オンライン個別指導という形式だからこそ、一人ひとりの生徒とじっくり向き合い、その子のペースや個性に合わせた、きめ細やかな声かけとサポートが可能です。
私たちは、学力向上はもちろんのこと、子どもたちが自信を持って未来へ羽ばたいていくための「心の土台づくり」も、同じくらい大切だと考えています。
まとめ:自信という最高の贈り物を子どもたちへ
中学生という多感な時期は、自己肯定感が揺らぎやすい時期でもあります。しかし、この時期にしっかりと自己肯定感の根っこを育ててあげることは、お子様の人生にとって、何物にも代えがたい、最高の贈り物になります。
今回ご紹介した10個の関わり方は、特別なことではありません。日々の生活の中で、少し意識を変えるだけで実践できることばかりです。
「褒める」という行為の奥にある、「認める」「受け止める」「信じる」という温かい気持ちを、ぜひお子様に伝えてあげてください。焦らず、比べず、お子様自身のペースで、その子らしい輝きを放てるように、そっと背中を押してあげられたら素敵ですね。
「うちの子の自己肯定感、どうしたら育めるか具体的に相談したい」
「オンライン個別指導塾Cheers!の教育方針や指導について、もっと詳しく知りたい」
「まずは話を聞いてみたい」「うちの子に合うか相談したい」
そう思われた方は、ぜひ一度、無料学習相談にお申し込みください。オンラインまたは対面で、経験豊富なスタッフがお話をじっくりお伺いし、お子様に合ったサポートや関わり方について、一緒に考えさせていただきます。無理な勧誘は一切ありませんので、安心してお問い合わせください。
無料学習相談はこちら(https://cheers-school.com/)