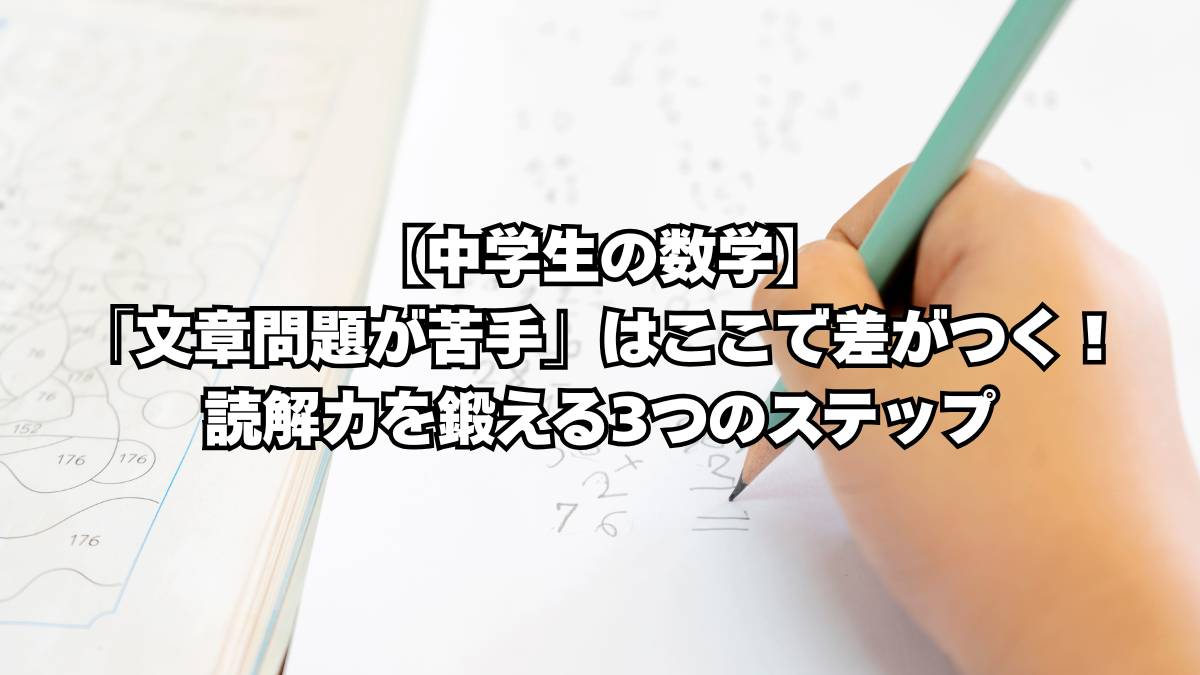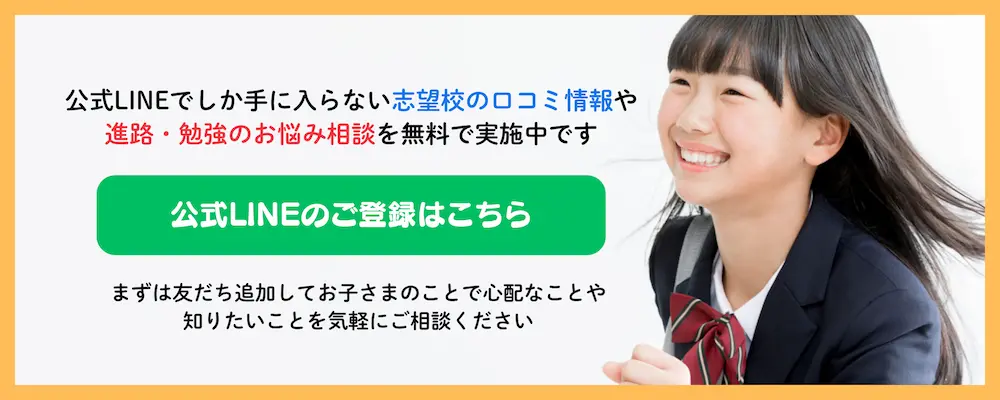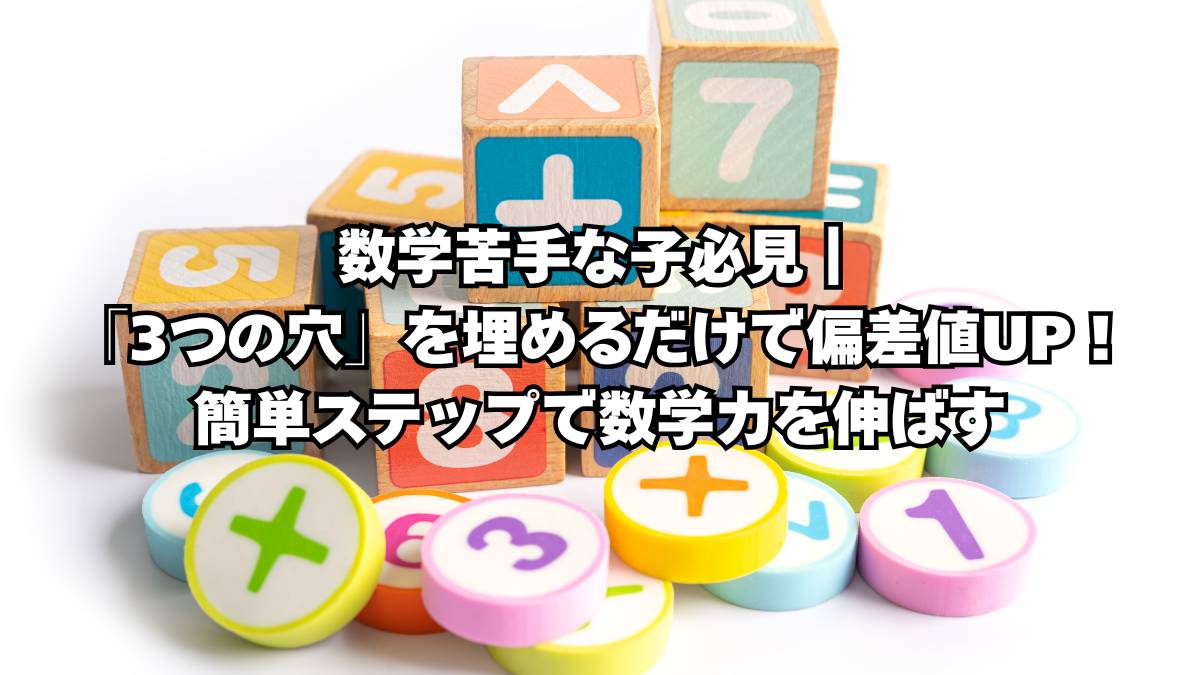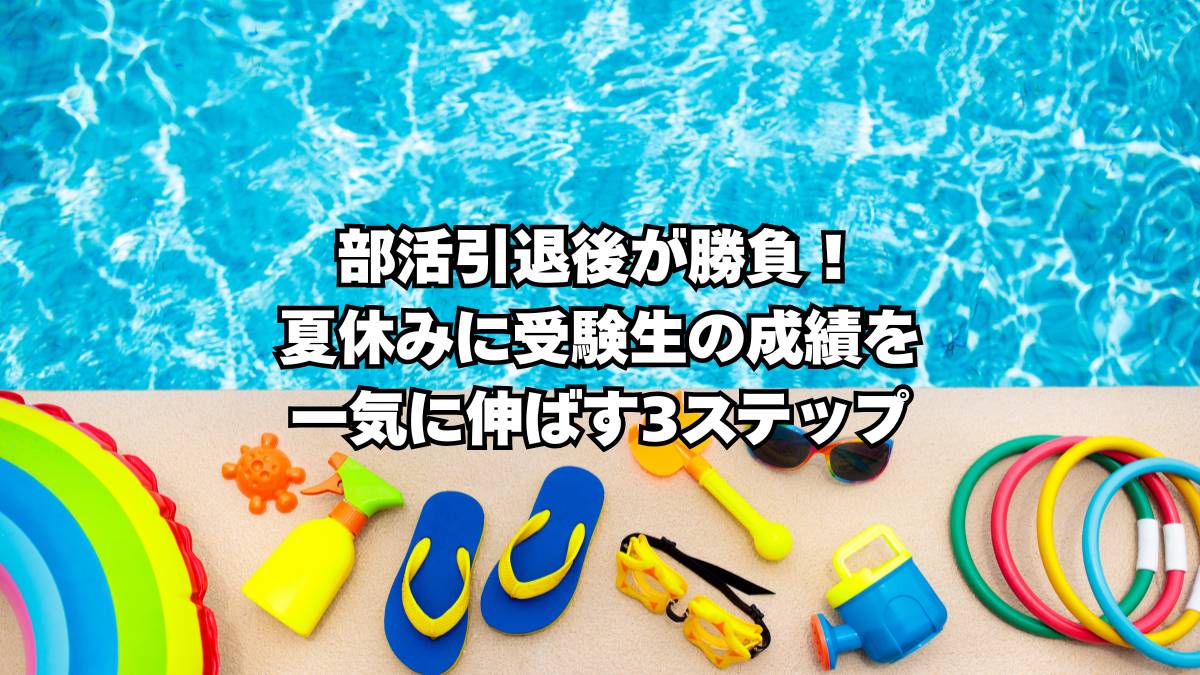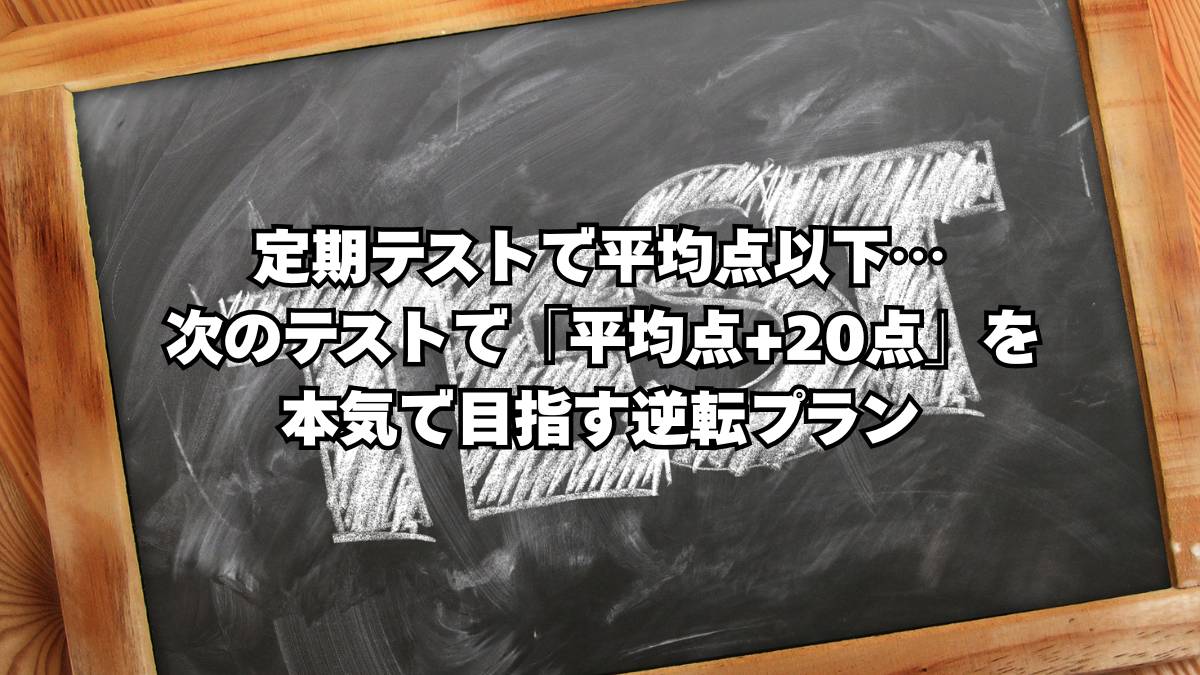こんにちは
自己肯定感を高めるオンライン個別指導塾Cheers!(@cheers.school)です
「うちの子、計算問題はスラスラ解けるのに、文章問題になると途端に手が止まってしまうんです…」 「式さえ立てられれば解けるはずなのに、問題文の意味がわからないみたいで…」
中学生のお子様を持つ保護者の皆様から、数学に関するお悩みとして非常によくお聞きするのが、この「文章問題」の壁です。せっかく計算力はあるのに、文章問題が苦手なせいで数学全体の成績が伸び悩んでいる、というケースは本当に多いですよね。
「算数の頃から文章問題は苦手だったから」「数学的センスがないのかしら」と、つい漠然とした「苦手意識」で片付けてしまっていませんか?
実は、その原因は「計算力」や「センス」といった曖昧なものではなく、もっと別の、具体的なスキルにあるのかもしれません。
今日は、多くの中学生がつまずく数学の文章問題の本質と、その苦手意識を克服するための具体的な3つのステップについて、詳しく解説していきます。
文章問題の正体は「翻訳作業」である
数学の文章問題が苦手なお子様の答案用紙をよく見ていると、ある共通点に気づきます。それは、「問題用紙が真っ白」であることです。
式を立てようとして考え込んでいるうちに時間が過ぎてしまい、何も書けずに終わってしまう。この状態の根本的な原因は、計算力以前の問題、つまり「問題文に書かれている日本語を、数学の言葉(式)に翻訳できていない」という点にあります。
例えば、英語の長文を日本語に訳す時、私たちはまず英単語や文法を理解し、文の構造を把握してから日本語に置き換えますよね。
数学の文章問題も、これと全く同じです。 問題文という「日本語」で書かれたストーリーを読み解き、登場人物や条件を整理し、最終的に「数式」という世界共通の言語に翻訳する。このプロセスこそが、文章問題を解くということの本質なのです。
つまり、文章問題で差がつくポイントは、計算力だけでなく、この「翻訳力」、言い換えれば「読解力」にあるのです。
文章問題の読解力を鍛える3つのステップ
では、どうすればこの「翻訳力」を鍛えることができるのでしょうか。私たちCheers!では、生徒一人ひとりのつまずきに合わせて、以下の3つのステップを丁寧に指導しています。
ステップ1:状況を「見える化」する(図や絵を描いてみる)
文章問題が苦手なお子様は、問題文の状況を頭の中だけで理解しようとして、混乱してしまいがちです。「速さ」の問題で登場人物が向かい合って進んでいるのか、同じ方向に進んでいるのか。「食塩水」の問題で、水を加えたのか、食塩を加えたのか。こうした状況がごちゃごちゃになってしまうのです。
そこで、まず初めに徹底するのが「図や絵を描いて、問題の状況を見える化する」ことです。
これは、決して特別なことではありません。例えば、「A君とB君が出会うのは何分後?」という問題なら、簡単な線分図を描いて、A君とB君のスタート地点と進行方向を矢印で示す。たったこれだけです。
絵を描くことで、文章という抽象的な情報が、具体的なイメージへと変わります。すると、「二人の距離の合計が、全体の距離になればいいんだな」といった、式を立てるためのヒントが自然に見えてくるのです。上手な絵を描く必要は全くありません。自分だけがわかる簡単なイラストで十分です。まずは問題用紙の余白を、図や絵で埋めることから始めてみましょう。
ステップ2:ゴールと登場人物(情報)を明確にする
次に、描いた図に情報を書き込みながら、「この問題のゴールは何か?」そして「ゴールにたどり着くための情報は何か?」を整理していきます。
国語の読解で「登場人物に丸をつけよう」と習ったのと同じです。文章問題に出てくる数字や条件(登場人物)に線を引いたり、丸で囲んだりして、一つひとつチェックしていきます。
そして最も重要なのが、「何を求められているのか(ゴール)」を明確にすることです。問題文の最後にある「~は何分後ですか?」「~の代金は何円ですか?」という部分を、最初に確認する癖をつけましょう。
ゴールが分かれば、そこから逆算して「この答えを出すためには、どの情報が必要だろう?」と考えることができます。闇雲に式を立てようとするのではなく、ゴールから逆算して情報を整理する。この習慣が、複雑な問題になればなるほど効いてきます。
ステップ3:「わからないもの」をx(エックス)として式を立ててみる
ステップ1と2で問題の状況が整理できたら、いよいよクライマックスの「翻訳作業」、つまり立式です。
ここで多くのお子様が、「x(エックス)って何のことだか分からない」とつまずきます。
xとは、難しく考える必要はありません。ステップ2で明確にした「求めたいもの(ゴール)」を、とりあえず「x」という箱に入れてあげるだけです。「求めたい時間」をx分、「求めたい代金」をx円、と置くことから始めます。
そして、ステップ2で整理した情報を使って、「=(イコール)」で結べる関係性を見つけ出し、式を組み立てていきます。
例えば、「リンゴ3個とミカン5個で850円」という情報があれば、「(リンゴの値段)×3 + (ミカンの値段)×5 = 850」という関係が見つかります。この時、求めたいのがリンゴの値段なら、そこをxと置けばいいのです。
最初から完璧な式を立てる必要はありません。まずは簡単な関係性を見つけて、イコールで結んでみる。この「トライアンドエラー」を繰り返すことで、日本語を数式に翻訳する感覚が少しずつ養われていきます。
まとめ
というわけで、今日お伝えしたかったのは、「数学の文章問題は、計算力だけでなく、読解力と翻訳力が鍵を握っている」*ということです。
そして、その力は、
ステップ1:状況を「見える化」する
ステップ2:ゴールと登場人物(情報)を明確にする
ステップ3:「わからないもの」をxとして式を立ててみる
という具体的なステップを踏むことで、誰でも着実に鍛えることができます。
しかし、これらのステップを、お子様が一人で、しかもテスト本番のプレッシャーの中で実践するのは、簡単なことではありません。どこでつまずいているのか、どう考えれば次のステップに進めるのかを、隣で優しくサポートしてくれる存在が必要です。
私たちオンライン個別指導塾Cheers!のマンツーマン指導で、この「3つのステップ」を一緒に実践してみませんか? お子様一人ひとりの思考の癖を見抜き、「どこで翻訳に困っているのか」を的確に突き止め、自信を持って式を立てられるようになるまで、根気強くサポートします。
記事を最後まで読んでいただきありがとうございました
オンライン個別指導塾Cheers!では、経験豊富で愛のある塾長が、一人ひとりの良いところを認めてあげて褒めながら、お子様の学力を伸ばしていくオンライン個別指導塾です
無料体験授業のご希望・子育てやお子様の学業に関する悩みやご相談など無料で承ります
いつでもお気軽にご相談ください!→LINEで無料相談